コラム
Media Innovation Lab
米国リテールビジネスのDX最新情報 【Media Innovation Labレポート20】
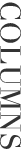
新型コロナウィルスの流行により生活者の行動が制限されたことで、生活者のデジタル化が急速に進みました。リテール(小売)においてもEC利用率が急拡大し、店舗の機能や購買行動に変化が生じています。こうした変化に米国リテールビジネスはどう対応し、DXを進めてきたのか、またそこから広告ビジネスにもどのような影響が考えられるのか――。博報堂DYメディアパートナーズイノベーションセンター 兼Media Innovation Lab(メディアイノベーションラボ※)の吉田弘(シリコンバレー在住)に博報堂DYメディアパートナーズ ナレッジイノベーション局兼Media Innovation Labの大野光貴が聞いていきます。
■コロナ禍で急拡大したアメリカのEC市場
大野
2020年は世界中で新型コロナウィルスのさまざまな影響がありましたが、アメリカにおいては、多くの州で外出が制限されたためショッピングモールやスーパーから人影が消え、購買行動が大きくECへとシフトしました。こうしたリテール(小売)ビジネスの動きは日本のDXにも大きなヒントになると思います。まずはアメリカのリテール業界の概要を教えていただけますか。
吉田
アメリカにはGMS(General merchandise store)と言われる大規模スーパーがたくさんありますが、最大規模を誇るのが、日本円で60兆円以上の売上があるWalmartです。リテーラーとして売上ランキングでWalmartに次ぐのはAmazonとなるようですが、コロナ禍でAmazonが相当追い上げているようです。そこへKrogerやCostco、Targetといった総合スーパーが続きます。ECで見るとAmazon一強で、それに次ぐのがWalmart。ただし、WalmartのECの売上はAmazonの5分の1以下です。続いて、e-bay、Apple、ホームセンターのHome Depo、Target,家電のBestBuyといったリテーラーが並びます。
大野
アメリカでは2020年にEC利用が急激に増加したようですが、日本とは何か異なる事情があるのでしょうか
吉田
まず、アメリカでは、パンデミック中は生鮮食料品や医薬品などの生活必需品の販売以外は完全に店を閉じなければなりませんでしたし、スーパーで生鮮食料品を買うにしても厳しい人数制限があり、入店待ちの行列に並ばなければ買えないという状況でした。そこで多くの人がECを利用するようになりました。宅配ロッカーが設置されている集合住宅も少なくありませんが、入りきらない荷物が外に溢れていることは日常茶飯事で、特に2020年4月から9月くらいはそのような状況でしたね。また、Walmartのようなビッグボックスと呼ばれる大規模店舗は、ネット注文された商品を店舗の外で受け渡すピックアップサービスも同時に行っていて、好評でした。

宅配ロッカーに入りきらない荷物(シリコンバレーの自宅アパートエントランス:吉田撮影)
大野
コロナによって買い物に行けなくなり、そこをECに頼ったことでECが拡大したわけですね。では、EC事業者やShopifyのようなECプラットフォーマー側にも何か変化はありましたか。
吉田
Shopifyはもともとカナダで生まれた、ECショップを簡単に開設できるというプラットフォームです。コロナ流行前から伸びてはいましたが、コロナを契機に急成長しました。いわゆる最近隆盛のSaaSビジネスで、決済や配達、コールセンターなどの機能を任せられるというもの。Shopify以外にも、BigCommerceなど何社か成長してきています。そうしたサービスを通じてEC店舗を持ちつつ、Amazonのマーケットプレイスにも出品するというように、両方の販売チャネルを活用する企業は少なくありません。またD2C企業も多数台頭していますが、ShopifyやAmazonへの出品を使い分けながら売上を伸ばしています。さらに最近は、Shopifyのようなテンプレート型ではなく、インターフェースは自由にデザインしたいというユーザーのニーズに応える形で、ヘッドレスコマースという、APIのみを提供するサービスも伸びています。このようにECプラットフォーマーがECへの参入障壁を下げたこともあって、リテール業界全体のEC比率は2019年の9.9%から2020年で15%と、大きく伸びています。

■企業の明暗を分けた、コロナ以前のDXへの取り組み
大野
ECが躍進したとはいえ、リテール全体の売上で見ると、やはり実店舗での購買が占める割合の方がまだ相当高いですね。Walmartのようなビッグボックスはコロナ禍においてどのように数字を伸ばしてきたのでしょうか。
吉田
生鮮品はAmazonでは買えませんから、必然的にWalmartを始めとする生鮮品を扱う店のピックアップも含めたECが伸びていきました。Walmartは2016年にJet.comというECのプラットフォームを買収、同社の社長をEC部門のトップに据えてDXを本格的に進めていましたし、Kroger もTargetも数年前から本腰を入れてECの整備を行っていました。ちなみにビッグボックス始めこうした大手リテーラーは自前のエンジニアを大量に抱えていて、たとえばWalmartは、シリコンバレーにWalmart Labs(ウォルマートラボ)という、5000人以上のスタッフを抱える巨大な開発部門があります。Krogerにも1500人ほどのエンジニアがいます。彼らが本気でDXに取り組んできたところへコロナが発生したので、その動きがさらに加速したという背景があります。
またコロナ禍では、先ほど少し触れたBOPIS(Buy Online Pickup In Store)と呼ばれる、オンラインで買い、店舗でピックアップするというサービスが定着していきました。店内にも入れない時期はPickup at Curb side――つまり駐車場でピックアップするという形式も登場。即日配送サービスもあるにはありますが、店舗が限られているほか配送料がネックになります。その点、アメリカだと車を持つ人がほとんどなので、お店でピックアップするスタイルが非常に便利だったわけです。これは前からあったサービスですが、コロナ禍によりニューノーマルの購買スタイルとして完全に日常化しましたね。今後もこのまま定着するのではないかと思います。
大野
なるほど。ではデパートや専門店はどうでしたか。
吉田
非常時において日用品以外は二の次になりますし、この1年、大半の期間は店を開けることすらかないませんでしたから、当然売上は大きく後退しています。高級デパートのNeiman MarcusやBrooks Brothersなどが次々と経営破綻したことは大きなニュースになりました。一方で生き残った企業というのは、コロナ禍前から着実にDXを進められていたということかもしれません。たとえばアメリカ全土に約1000店舗を抱えるデパートのKholsは、Amazonで購入した商品をKholsの実店舗で返品できるという新たなサービスを始めました。そもそも日本と比べアメリカではAmazonの返品が非常に多いのですが、手続きの煩雑さが不評でした。そこへ、最寄りのKholsに持っていくだけで返品手続きができ、さらにKholsのクーポン券をもらえるということで人気となっているようです。Nordstromも、商品は置かずにオンラインで買った商品のピックアップおよび返品対応だけを行う店舗を出すなど、ECを前提にした店舗展開を始めています。返品コストをいかに下げるかはもともと課題としてあったので、そこにうまく対応した例だと思います。
専門店も、もちろんピックアップやデリバリーサービスを展開しています。そのなかでも特にECが進んでいる例としては、キッチン用品の専門店Williams Sonomaがあります。ここはECでの売上が全体の7割を超えているのですが、早くからDXに力を入れていて、バーチャルで料理教室を開いたり、自分の部屋に商品がフィットするかオンラインでわかるようなサービスなどを展開したりしていて、DXによって上手にブランド体験を提供しながらファンづくりを行っています。
大野
コロナ禍を境に、企業によっても明暗が分かれたようですね。
吉田
コロナ前にDXをどこまで進められていたかが、大きな差となって出たような気がします。DXと並行してバックエンドの仕組みも整備しておかないと、店舗とECの在庫を調整しながらのピックアップサービスもできませんし、フルフィルメントと言われる流通システムそのものを大きく変えなければならないケースもある。当然自前で多くのエンジニアを抱えていた企業は強みを発揮できていましたね。日本にはそこまで内製体制が整っているリテーラーはないのではないかと思います。
■コロナ前後で生まれたさまざまなDXの動き
大野
今後の展開としてどういった店舗形態、技術などに注目していますか。
吉田
アメリカはこれまで、高所得者層、中所得者層、低所得者層といった大まかな社会階層に応じ、似たような形態の店舗を全国に多数展開させるというリテール企業が多かったのですが、それが少し変わってきているような気がします。というのも、ピックアップサービスに特化したお店や、ショールームのように体験するだけのお店、あるいはダークストアといって、閉鎖してしまった店舗を倉庫として活用する例もたくさん出てきている。郊外ならこんな店、高級住宅街ならこんな店というように、場所の特性に応じてより細分化されたポートフォリオで出店戦略を考える必要性がリテール業界全体で説かれ始めています。
大野
テクノロジーの進化によって出てきた新しい店舗形態についてはいかがですか。
吉田
AmazonGoが一般に公開されたのは、3年くらい前になりますね。事前にAmazonにログインしてから店内に入ると、自分が入店したことをAmazonが認識し、店内に設置された多数のカメラとセンサーによって何を手に取ったかが把握され、持ち帰った品はあとでAmazonにチャージされるというシステムです。手ぶらで店に行きレジを通さずに買い物ができるということで先進的だと話題になりましたが、実際に採用するケースが出てきています。アメリカの空港内によく入っているHudsonは、AmazonGoと同じ技術を使って無人店舗を導入しましたし、Standard RecognitionというAmazonの競合会社も、同じような技術のライセンス販売で成長しています。無人店舗は実験のフェーズから実用のフェーズに入ったと感じます。
大野
新しい購買体験をつくるための試行錯誤も行われているのですよね。
吉田
今年になって、デジタルとソーシャルにエンタテインメントの要素を組み合わせた、ショッパーテイメントというキーワードが出てきました。きっかけは中国でプラットフォーム企業が展開するコマースで、動画を見ながら商品を買うサービスが非常に盛り上がっていたこと。アメリカにとってもこれは刺激的だったようで、同様のサービスを行うベンチャー企業がいくつも出てきました。基本的には商品を紹介する動画がたくさんあり、ユーザーはそれを見て“いいね”などと反応する。AIで動画にタグがついていて、商品情報とリンクさせ、購買へとつなげる。もしその動画を通じて商品が買われれば動画のクリエイターに何%か入るといったシステムです。他には、友人4~5人と同じ画面を共有し、「これどうかな?」などと話しながら購買できるような、ショッパーテイメントの機能を入れたアプリも誕生しています。

■広告ビジネスに影響を与える大手リテーラーの動向
大野
広告ビジネスにおいて、リテールビジネスのDXはどんな影響を与えるでしょうか。
吉田
既存の広告ビジネスにとってもリテールデータ活用が進んでおり、1stパーティーデータ保有者として重要性が増しています。すでに、Amazonは広告プラットフォーマーとしても巨大な存在になっていますが、他のリテーラー達もDSPなどアドテクノロジーの会社との連携を進めていて、Walmartは既に年間かなりの広告ビジネスを行っているようですし、他のリテーラーもチャレンジを進めています。DXの進んだリテーラーが所有する1stパーティーデータは、オンライン、オフライン双方の生活者行動、購買履歴という他のプレーヤーが持ちえない貴重なデータであることから、このデータを活用したデジタル広告配信が可能となり、広告主からも注目され始めています。
大野
他に、広告やマーケティングではどんなポイントが重要になるでしょうか。
吉田
リテール業界のDXの流れは加速しますが、一方、体験価値をどう生活者に与えるかも重要要素になります。そういう意味で、ブランドの世界観を伝える機能というものが非常に大事になります。かつてはオンラインで商品やブランド体験をさせて、実店舗で購入してもらうという手法でしたが、この20年でむしろ店舗は体験の場所、オンラインは購入する場というように逆転しました。改めて、既存の店舗やスペースを、ブランド体験を提供する場としてどう設計し直すか、そしていかにマーケティングの回路に位置付けるかが大事だと思います。コロナ禍で一時止まったとはいえ、各メーカー、ブランドが、こぞってポップアップストアや体験型施設を展開させています。そうした動きはコロナ禍が落ちつくと一層顕著になると思います。
大野
日本でも、小売のデータ活用を広告領域にも広げる動きが活発化してきています。今回お話しいただいた米国のリテールビジネスのDXを参考に、今後日本国内で起こりうる変化を読み、メディアのDXをリードしていくことが大事ですね。
今日はありがとうございました。

※Media Innovation Lab (メディアイノベーションラボ)
博報堂DYメディアパートナーズとデジタル・アドバタイジング・コンソーシアムが、日本、深圳、シリコンバレーを活動拠点とし、AdX(アド・トランスフォーメーション)をテーマにイノベーション創出に向けた情報収集や分析、発信を行う専門組織。両社の力を統合し、メディアビジネス・デジタル領域における次世代ビジネス開発に向けたメディア産業の新たな可能性を模索していきます。

吉田 弘
博報堂DYメディアパートナーズ イノベーションセンター
1988年博報堂入社。事業局、研究開発局を経て、2004年より博報堂DYメディアパートナーズへ異動。メディア環境研究所長、メディアビジネス開発センター長を経たのち、2018年よりイノベーションセンター(シリコンバレーオフィス)エグゼクティブディレクター。20年より、Media Innovation Lab (メディアイノベーションラボ)海外拠点リーダーを兼務。

大野光貴
博報堂DYメディアパートナーズ ナレッジイノベーション局 情報マネジメント部
ラジオ局のビジネス企画開発部、メディアビジネス開発センター、データドリブンビジネス開発センターなど新規開発系部署を経て、2018年よりナレッジデザイン局(現ナレッジイノベーション局)で主に海外のテクノロジーやメディアにおけるDXを調査。クリエイティブ&テクノロジー局テクノロジーソリューション開発グループ複属。
★【Media Innovation Labレポート.1】米国動画配信サービスの最新動向
★【Media Innovation Labレポート.2】米国スポーツビジネスの最新動向
★【Media Innovation Labレポート.3】 「投げ銭」市場最前線(前編)
★【Media Innovation Labレポート.4】 「投げ銭」市場最前線(後編)
★【Media Innovation Labレポート.5】 世界のゲームビジネス最新動向
★【Media Innovation Labレポート.6】 量子技術が未来を変える(前編)
★【Media Innovation Labレポート.7】 量子技術が未来を変える(後編)
★【Media Innovation Labレポート.8】 様々なビジネスにインパクトをもたらすゲームエンジン ~ゲームからエンタテインメント、そして産業利用へ~
★【Media Innovation Labレポート.9】深圳オフライン店舗とリアル体験の進化
★【Media Innovation Labレポート.10】 DXによってメディアと広告ビジネスはどう変わるのか ──メディアイノベーションラボ新春企画
★【Media Innovation Labレポート.11】 ハプティクスがコミュニケーションの未来を変えていく
★【Media Innovation Labレポート.12】 コロナ禍で活況!「音声配信サービス市場」の最前線
★【Media Innovation Labレポート.13】 CES2021 ~メディア・コミュニケーション視点での注目トピック~
★【Media Innovation Labレポート.14】 音声SNSのこれから
★【Media Innovation Labレポート.15】 ペットの家族化により進化する、ペットテック・ペットメディア
★【Media Innovation Labレポート.16】マーケティング効果向上へ進化を続ける「スーパーボウル」
★【Media Innovation Labレポート.17】知っておきたいNFTの最新事情とビジネスの可能性(前編)
★【Media Innovation Labレポート.18】知っておきたいNFTの最新事情とビジネスの可能性(後編)
★【Media Innovation Labレポート.19】プラットフォームとしてのゲーム上で拡がるクリエイターエコノミーの可能性 ~Robloxのケース~































