コラム
動画だけじゃない?
いまさら聞けない“OTT”領域のビジネスとその可能性
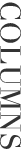
コロナ禍の影響もあり、OTT業界はいま一層の隆盛を見せています。加速度的に成長しているOTTビジネスの実態とは、そして今後の可能性は――。今年からOTTアカウント推進に本格的に取り組む博報堂DYメディアパートナーズ統合アカウントプロデュース局 OTTアカウント推進部の山本浩二、青木登、藤本将晃、同局AaaSアカウント推進二部の真野翔一の4人に、博報堂DYメディアパートナーズナレッジイノベーション局兼メディア環境研究所の斎藤葵が聞きました。

■コロナ禍に大きく後押しされたOTT市場
斎藤
今日は皆さんに、現在急成長を見せているOTT領域ビジネスについていろいろとうかがっていきたいと思います。まずは、そもそもOTTとは何かということから教えていただけますか。
山本
OTTとは“Over-the-top”の略で、基本的にはインターネット回線を通じて提供されるすべてのサービスを指し、デジタル動画媒体、オーディオ媒体、屋外のサイネージ媒体全般を総称する言葉です。テレビやラジオなどいわゆる4大マスメディアという成熟産業から派生しながらも、近年目覚ましい成長を遂げている新しい市場です。

斎藤
具体的にはどういったサービスや配信モデルがあるんでしょうか。
藤本
動画でいうと月額制で動画配信するサブスクリプションモデルと、AVOD(Ad-supported VOD)、つまり広告型動画配信サービスの2つに大別されます。前者でいうとNetflixやhulu、AmazonPrimeなどが知られていますが、広告会社である私たちがメインで扱っているのは後者。メディアとしてはたとえばYouTubeをはじめ、TVerやABEMA、GYAO!、DAZN、SPORTSBULLなどさまざまなメディアがひしめいている状況です。またSpotifyやradiko、ラジオクラウドといったオーディオ広告はもちろん、交通広告DODMなど、インターネット接続されているサービス全体に注力している状況です。

斎藤
ありがとうございます。さまざまなメディアが登場するなかで、生活者のメディア接触状況なども変わりつつあると思いますが、実際のところを教えていただけますか。
真野
4大マスメディア全盛だった頃はすべてオフラインだったわけですが、インターネットの進化に伴いサービスがオンライン化されていき、生活者もそれを体験するという形になってきました。数年前から取り組みが進んできたDXもコロナ禍でより加速化し、オンラインの需要は高まり続けています。一方で生活者は、オフラインオンラインに関わらず、便利なものを使うという意識でいます。生活者にしてみればダイナミックなシフトというよりは、非常にスムーズに継ぎ目なく変化が起きていて、特に意識することなくよりオンライン化したサービスを活用しているという状況かと思います。

斎藤
若年層ほどテレビ単体のリーチが難しいなど、生活者のメディア接触傾向の変化もOTT隆盛の背景にあるでしょうか。
真野
そうですね。テレビに替わるさまざまなサービスの選択肢が出てきたというのと、土日が必ずしも休みではなかったり、生活者の働き方も多様化してきました。地上波に依存する生活スタイルから、オンライン含めたさまざまなサービスを活用できる生活スタイルに変化してきたことが、いわゆる“若年層のテレビ離れ”と言われる事象につながっているのかなと思います。ただ重要なのは、地上波から離れているだけで、決してコンテンツ離れしているわけではないという点ですね。
山本
テレビの受像機を持たない若年層も増えていますよね。そもそもTVerやABEMAなどは、そうしたユーザーの動向に合わせて、「だったらスマホでも見られるようにしよう」ということでオフラインから飛び出してきたもの。受像機がなくてもすべての国民がテレビのコンテンツを見られるように整えられてきたプラットフォームを、我々がいま扱わせていただいているという捉え方でいます。
斎藤
なるほど。先ほど少し触れられたコロナ禍の影響について、もう少し詳しく教えてください。
山本
我々が扱っている広告型動画配信サービスの状況からわかるのは、視聴のかたまり時間があればあるだけ、視聴数は伸びるということ。サブスクリプション動画配信サービスも会員数を大きく伸ばしていますが、特にこの2年、外出自粛が要請されていた間は家の中で動画視聴にあてる可処分時間が増加するなど、コロナによる巣ごもり需要の高まりがダイレクトに影響していると思います。またそれと同時に各プラットフォームのコンテンツ総量も非常に増えています。良質なオリジナル作品や海外で人気の作品などがどんどん拡充されていて、見るべき面白いコンテンツが溢れているところへコロナがやってきました。それによって必然的に視聴機会が増えているのかなと思います。ちなみにコンテンツ周りについてもう少し詳しく言うと、アニメでもドラマでも、地上波オフラインで放送されたものをオンラインで配信しようとすると、さまざまな権利者団体が関わってきます。そこで、すべてのコンテンツをオンラインでも並べられるような権利処理を、各テレビ局が積極的に進めています。いずれは可能な限り全番組配信するんだという、テレビ局側の努力というのも非常に大きいです。

斎藤
そのテレビ局の方は、この変化にどう対応しようとされているのでしょうか。
藤本
やっぱりテレビ局の制作能力は高いですし、コンテンツ自体の魅力度は変わっていないと思います。そこにデバイスの変化とサービスの多様化があり、テレビ画面もさまざまなコンテンツを受像するモニターと化してきています。生活者からすると、デジタルと地上波の境目はどんどんなくなってきているわけです。コンテンツ力を武器に、地上波~デジタルといった垣根を越えてビジネスチャンスを広げていくと思います。
山本
放送局内部の方からすると、より面白いコンテンツをつくるんだという気概を持ちつつ、そのためにもデジタルを積極的に活用しようとされているのだと思います。実際、オウンドでつくったショートストーリーだとかスピンオフドラマをYouTubeに投稿することで番組を盛り上げるといった手法も増えている。映像制作の手法、コンテンツのつくりかたも、どんどん進化しているという実態だと思います。
■OTT各領域のビジネスに起きている変化
斎藤
地上波のコンテンツが公式で見られるTVerは、2015年10月からサービスが始まりました。山本さんはその立ち上げ時からずっと前線にいらっしゃったわけですが、当時から最近までの視聴形態の変化について教えていただけますか。
山本
TVerは2014年、当時の民放連井上弘会長の発言もあり、放送局5局が揃ってオンラインで番組コンテンツを掲出できる場として独自開発され2015年10月からスタートしたものです。当然ながら、2006年あたりで日本に上陸し一世を風靡しはじめたYouTubeに対抗しうる映像配信プラットフォームをつくるという狙いもありました。当初は各局約10番組からスタートしたのですが、権利処理がうまく進まず、コンテンツ量はなかなか伸ばしづらい環境だったことを記憶しています。そこから全局それぞれがさまざまなPRをしながら、権利処理も進めていくなかで、コンテンツ量を増やしていった。いまでいうと、権利処理が常々発生する情報番組や報道番組、海外ロケものなどを除くドラマやバラエティー番組はほぼすべて配信するというところまで来ました。新作映画の公開に合わせて、同じ俳優の過去作品を集中的に配信するなど、メディア横断的に連鎖反応を狙うような動きも出ています。コンテンツが増えることでユーザーも増え、ビジネス成長しているところです。
斎藤
コンテンツを見る機会が増えると共に、見る層も広がっていきそうですね。
山本
新たなチャンスを狙って投資を続けている状況だと感じます。まだまだ実験的な段階ではありますが、誰でもどこでもどんな時にでもコンテンツを見られる環境づくりに、全力で取り組んでいるところだと感じます。
斎藤
なるほど。一方で、インターネットにつながったテレビ、いわゆるコネクテッドTVの市場もぐんぐん伸びてきています。そのあたりのビジネスにはどんな動きが出てくるでしょうか。
真野
最近は、テレビを新たに購入するとリモコンにすでにYouTubeのチャンネルボタンがあるなど、地上波とデジタルがシームレスになりつつあります。ユーザーからすれば、地上波のタイムテーブルにとらわれることなく、自由にタイムフリーで見ることができるわけですから、コネクテッドTVの利用はどんどん浸透していき、市場としても成長するのではないかと思います。ただ、地上波で見るCMもコネクテッドTVで見るCMも見た目はまったく一緒になるので、どう両者を連携しながら活用していくのかは今後の焦点になりそうですね。各住戸や施設へのWI-FI整備が進んでいることや、5Gの開始など、通信やデバイスの進化もこうした動きを後押ししています。この傾向は全世界的なものです。
斎藤
なるほど。ありがとうございます。では音声市場についてはどんな動きがありますか。
青木
僕自身は地上波のラジオのセールスを15年ほどやってきたなかで、ラジオの聴取率の低下は年々感じるところでした。そんななか2010年にradikoというインターネットラジオの配信サービスが始まりましたが、開始以降起きたもっとも象徴的な変化は聴取者の平均年齢層が50代から40代へと下がったことです。これは、10~30代のリスナーが増加したことが背景にあります。また、地上波のラジオ聴取者は変わらず減少傾向にあるなか、radikoやSpotifyなどのMAU数やDAU数は右肩上がりで増えている。音声メディアの特徴として、声だけで伝える独自の世界がありますが、その支持者はまだまだ非常に多くいるということだと思います。また、テレビ受像機は家族とシェアするものだと思いますが、ラジオはどこまでいっても個人で使う、パーソナルユースに特化したメディア。スマホを通してデジタルで聞くというスタイルによりマッチしているのだとも思います。
ちなみに深夜ラジオのリスナーには意外と女性が多いのですが、その理由はおそらく、ラジオの向こうにいるパーソナリティには本心を吐露できるとか、自分と同じ境遇の人の話に共感しやすいといった傾向が、女性の方が顕著だからという気がします。あくまでも私見ですが。

斎藤
確かに私の所属するメディア環境研究所の調査などでも、夫や子どもが帰宅するまでの時間に料理をしながら、ラジオを聴いてリラックスして過ごすという主婦の方がいらっしゃるという話や、若年層の女性が、映像や写真と違って声はフェイクできないので、推しのタレントの声が聴けるラジオは信じられるといったような話があります。
青木
もう一つ、昔からラジオは、運転や料理、勉強をしながら聴けるというメディア特性が若年層や忙しい主婦層に支持される理由と言われています。デバイスがスマホに代わって持ち歩けるようになり、その傾向は一層強まっています。
真野
僕の部署で若年層のコロナ前後の接触メディア変化を調べたところ、コロナ以降に接触する機会が増えたメディアとして、Z世代はSpotifyを挙げています。これは面白いデータだと思いました。実際に電車内でもたくさんの人がイヤホンを付けていますし、ディスプレイを見なくてもいい分、音声メディアは拘束感がなくて自由なのがいいのかもしれません。
青木
それから音楽だけじゃなく、声のブログやポッドキャストなどコンテンツも多様化しています。たとえば人気サッカー選手が普段考えていることを話したりファンからの質問に丁寧に答えてくれるようなコンテンツが人気だったりしますが、演者にとっても、出演時間の拘束もありませんし、映像と違って着飾る必要もない。双方ともメリットの大きいコンテンツだと思います。
山本
確かにオーディオコンテンツは、映像と比べるといい意味で簡易的につくることができる。そこもビジネス上の大きなポイントになりそうですね。
■博報堂DYグループだからこその強みと可能性
斎藤
では博報堂DYグループとしてOTTに取り組むにあたり、これまでのオフラインのメディアと比べた時の可能性、また課題などをお聞かせください。
藤本
これまでテレビでは「ステマ」や「仕込み」が問題視されることがありましたが、我々が携わった番組制作の例だと、PR表記をつけ、スポンサードされているコンテンツであることを明示したうえで、クライアントの伝えたいことやニーズに合わせたコミュニケーション設計、コンテンツ制作を実現しています。デジタルの特長を活かしてよりピンポイントでターゲットにアプローチすることも可能ですし、よりクライアント課題に寄り添った深いコミュニケーションができるようになったと感じています。過去番組の活用も地上波よりハードルが低いですし、よりクライアント課題にマッチさせた形で柔軟につくり込みができるといった利点があります。また、デジタルだと、地上波と比べて少額からでもトライアル的に広告出稿できるので、スポンサーの幅も広がっています。
斎藤
なるほど。逆に課題としては何がありますか。
藤本
「広く届ける」という点においては、地上波テレビのリーチ力は圧倒的です。それに比べるとまだまだ、というところはあります。リーチの幅、視聴者の幅に関してはもっともっと伸びしろがある。ここにさらにブーストをかけていくことが課題であり目標です。
山本
そうですね。大事なのは、やはり最初にコンテンツを出すのは地上波だということ。それは大前提として変わらないと思います。そしてあくまでも、デジタルと地上波が補完し合いながら、双方のビジネスが伸びていく方向を僕らは目指しているということです。今後また大きなシフトチェンジが起こるかもしれませんが、そのときに備える意味でも、まずはこのOTT領域を成長軌道に乗せるということがポイントだと思います。
斎藤
いまある成熟市場をベースに、この成長市場を拡大していく、ということですね。
では、何か博報堂DYグループならではの強みはありますか。
藤本
我々が関わる領域は大きくコンテンツとメディアプランニングの二つに分かれますが、コンテンツ領域において言えば、関わらせていただいている案件数はおそらく業界随一です。さまざまなコンテンツとタイアップして番組を一からつくったり、そのIPを使ってさらにビジネスを拡大させるといったアプローチ事例は多数あります。いま注目しているコネクテッドTV領域においても、体系づくりや商品パッケージングといった点においては業界で一番進んでいるという自負があります。
真野
我々もまさにそうですが、いまこの領域を担っているのが、地上波のテレビやラジオに長らく関わってきて知見を積み上げてきたメンバーです。そのメンバーが、デジタルと同じ統合アカウントプロデュースという部署に所属している。こうして両方の脳みそで戦い方を考えながら進めていけるというのは、総合代理店ならではの強みでしょう。テレビを熟知しているからこそコンテンツ軸の話もできるし、コネクテッドTVなら地上波目線の文脈でもスマホやPCなどデジタルデバイス目線の文脈でも語れるメンバーが担当している。両方の可能性を追える体制が整っているのは大きな強みだと思います。
山本
さらに言えば、博報堂DYメディアパートナーズという社名が示すように、我々はメディアのパートナーとして一次情報を素早くとれる立場にある。これは昔から変わらない価値です。局との向き合いのなかで、素早くキャッチした一次情報を3000社以上のクライアント様に対して供給することができる。これは情報戦線において、他社にない唯一無二の武器となっています。さらに、僕らは媒体が持つ情報発信力だけでなく、番組制作力や取材力、ユーザーとのつながり、あるいは社会全体のトレンドをキャッチする力といったさまざまな媒体社アセットをフルに活用させてもらうこともできます。そうすることでクライアントに別解を提供することができる。これは総合広告会社としても非常に大事にしていることですし、大きな意味があることだと思います。
斎藤
では今後我々にかかわるビジネス全体としてのOTT市場はどう変化していくでしょうか。最後にお聞かせください。
真野
今後は、形式はどうあれ「いかにユーザーに届けるか」という統合プランニング的な考えが必要になってくると思います。動画で伝えるのか、音声で伝えるのか、あるいはタクシーの車内で伝えるのか…それぞれの媒体やデバイスによってクリエイティブもターゲティングも変わっていくでしょうし、いままさにその最適解を探っているところでもあります。いずれすべてがつながっていく世界に向けて、その解をいち早く見極めるためにも、トライアンドエラーを繰り返しながら最適な掛け合わせを探っていくことが必要だと思います。
青木
そうですね。そしてTVerにしろradikoにしろ、忘れてはならないのは、基本となるコンテンツは地上波から生まれているということ。そこにきちんとコミットしていなければ、この文化は続かないとも思う。放送局がものづくりをしているからこそ、僕らもそのコンテンツを楽しむことができている。それを忘れることなく、僕らも一緒に、「いま一番面白いものは何か」「いま何が必要か」といったことへの追求を止めないことが大切なのではないでしょうか。足元をしっかりと見続けるということが、今後ますます求められるのではないかと思います。
斎藤
よくわかりました。今日はありがとうございました!


山本 浩二
博報堂DYメディアパートナーズ
統合アカウントプロデュース局OTTアカウント推進
部長
2006年博報堂DYメディアパートナーズ入社。テレビタイムビジネス局の局担・業推を経てプレゼントキャスト社(現 株式会社TVer)へ出向。その後、MPに帰任し動画ビジネス局にてTVer、ABEMAセールスを推進。2021年よりOTTアカウント推進部にて動画メディアに加えてオーディオアド、DODMも担当。

青木 登
博報堂DYメディアパートナーズ
統合アカウントプロデュース局OTTアカウント推進部
メディアプロデューサー
1999年博報堂入社。初任配属は営業担当。2003年10月に博報堂ラジオ局へ異動、同12月に博報堂DYメディアパートナーズラジオ局へ承継~2019年まで16年間ラジオを担当。2019年統合アカウントプロデュース局デジタル業務推進部へ異動。2021年よりOTTアカウント推進部にて動画・音声・ODM領域を担当。

藤本 将晃
博報堂DYメディアパートナーズ
統合アカウントプロデュース局OTTアカウント推進部
メディアプロデューサー
2012年博報堂入社。通信系クライアントの営業(デジタル・制作)を担当後、
MPテレビタイムビジネス局の局担を経て、2019年より現在のOTT領域を担当。
動画市場の新指標「有効視聴単価」の開発をはじめ、「どっちの料理ショー」復活企画など様々なコンテンツ案件も企画。

真野 翔一
博報堂DYメディアパートナーズ
統合アカウントプロデュース局AaaSアカウント推進二部
メディアプロデューサー
2012年博報堂DYメディアパートナーズ入社。テレビタイムビジネス局の局担、旧博報堂DYデジタルでのプラットフォーマー担当を経て、2019年より動画領域におけるプログラマティック配信やデータソリューション・広告商品開発を担当。

斎藤 葵
博報堂DYメディアパートナーズ
ナレッジイノベーション局 ナレッジマネージメントグループ ナレッジビジネスプロデューサー 兼 メディア環境研究所 上席研究員
2002年博報堂入社。雑誌・出版ビジネスを中心としたメディアプロデューサーを経て2016年より現職。現在はメディア・テクノロジー・デジタルマーケティング業界のプレイヤーとのビジネスマッチングやディスカッションの場や各種オンラインセミナーの企画・運営・プロデュースを行う傍ら、当サイトの編集部員として取材・発信活動も行っている。































