コラム
広告会社・メディアビジネスのDXとは?
データ×クリエイティブで広がるコンテンツ開発と、ローカルメディアならではのデータの活かし方
【全広連 秋のシンポジウム レポート】
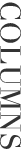
生活者がデジタルを自由自在に使いこなす今、生活者と企業との間を結びつける広告会社やメディア企業のDXも進んでいます。単にデジタル広告を売買するのではなく、デジタルを生かした新しい形のコンテンツや広告企画が次々と生まれています。講談社にてメディアビジネス改革を推進する長崎亘宏氏と、博報堂DYメディアパートナーズでデータを使ったコンテンツ開発を手掛ける篠田裕之による各講演、そして両者によるトークセッションからは、データとクリエイティブを掛け合わせた最先端の取り組みがうかがえました。
本稿では、2021年11月15日に岡山にて開催された「全日本広告連盟 秋のシンポジウム」の模様をお届けします。
読者コミュニティの価値に注目、「脱・旧雑誌広告営業」
第1講座として、長崎氏より「講談社メディアビジネスレビュー デジタル基点における“雑誌”と“出版社”の再定義とは」と題し、5年間に及ぶ同社のビジネス改革が詳細に語られました。
「2015年が、講談社のターニングポイントだった」と長崎氏。それ以前に本業で赤字転落を経験し、同年の年頭所感にて社長が「出版の再発明」を掲げたことから、改革が始まりました。紙媒体にこだわらず、例えば雑誌なら電子書籍やWeb、アプリなどを含めて「パブリッシングである」と定義。それぞれの読者の世代やライフスタイルに合わせて柔軟に形を変え、映像化や海外展開などの事業の多層化とメディアアライアンスを強化した結果、2020年度は創業以来初めて事業収入(電子版販売収入+ライツ収入)が紙媒体の販売収入を上回りました。
同時に、広告収入もデジタル広告と雑誌広告が6:4になっています。とはいえ、ここまで漕ぎ着けるには、従来型の広告営業から大きく脱却することが必要でした。
「2010年からの5年間で、広告収入は半減。デジタルメディアはスケールするのに時間がかかるので、コンテンツのデジタル化を進めながら、広告はデジタルを基点とした企画力強化と結果の可視化に注力してきました。脱・枠売りであり、脱・旧雑誌広告営業です」

出版社と読者の関係も見直し、読者コミュニティの価値に焦点を当てたことも奏功しています。例えば女性向けWebメディア「mi-mollet(ミモレ)」では、月額5,500円の有料会員制度「ミモレ編集室」を設け、編集企画に参加したりする活動が好評だそうです。

現在は、同社の媒体を束ねた広告配信プラットフォーム「OTAKAD」や、広告主および広告会社向けの情報ポータル「C-station」、オンラインに移行したビジネスイベント「講談社メディアカンファレンス」などを通じて広告主企業に貢献。長崎氏は「読者に響き、広告主の成果につながる『追いかけたくなる広告』を提供したい」と講演を結びました。
AIがカレーのレシピを開発! 高知放送×レシピサイトの取り組み
第2講座に登壇した博報堂DYメディアパートナーズの篠田は、データサイエンティストとしてデータ分析に基づくマーケティング支援に従事しています。今回は「データにできない想いはあるのか -データサイエンスを活用したメディアプラニング/コンテンツ開発-」と題し、博報堂DYグループが提唱する「AaaS(Ad as a Service)」の考え方を軸に、ローカルメディアの支援事例を紹介しました。
データとローカルメディアの関係において、篠田が挙げるポイントは3つ。ひとつは、データとデジタルはローカルこそ相性が良いこと。2つ目は、データは効果最適化だけでなくコンテンツ開発にも活用できること。3つ目は、ローカルだからこそ単発ではなく継続的な仕組みづくりができることです。
これらを体現する事例のひとつが、高知放送が2020年1月4日に放送した特番「人工知能で創り出せ!未知なるご当地カレー かまいたちの『AIカレー研究所』」です。ビッグデータを使った新しい番組企画を検討していた高知放送と、自社データのさらなる有効活用を模索していたレシピサイトを結び付け、高知県民のレシピ閲覧データを分析して「県民が好むカレーをAIが導き出す」という企画に落とし込みました。

放送前にレシピサイトで番組を告知し、番組の最後ではレシピサイトへ誘導する、Web×テレビの相互送客も実施。
「こうした事例の裏側で、視聴ログの分析を通して、番組ごとに広告効果の高い広告主を選定しご提案するなど、メディアプランニングの精度向上にも取り組んでいます。ローカルメディアはエリアの生活者へのリーチはもちろん、地元産学連携への影響力も大きいので、その価値をビッグデータとデータサイエンスで下支えしていきたいと思います」。
10年後、自社の仕事は存続しているのか
ここからは、全日本広告連盟執行理事の中井良博氏の進行によるトークセッションを紹介します。

中井
お二人とも、学びの多い講義をありがとうございました。さて、まず今回のシンポジウムの背景を少しご紹介したいと思います。
メディアビジネスや広告ビジネスの革新が進み、都市部を中心にデジタル化やグローバル化が大変な勢いで進んでいます。一方、地域では改革の必要性はわかりながらも、実践としては取り残されているのではないか、という危機感があります。その課題を真正面から捉え、「メディア/広告業のDXを考える」と掲げさせてもらいました。
東京の一極集中が進み、これ以上のギャップが広がる前に、地域においていかにメディアと広告の改革を実現するか。その観点で、お二人により掘り下げてお話をうかがっていきます。
まず長崎さん、「出版の再発明」というキーワードがありましたが、5年をかけてそれが実現しつつある要因はどういったところにあるとお考えですか?
長崎
ひとことで言うと、トップダウンであったことがいちばん大きかったと思います。ある意味、創業100年以上になる事業の自己否定でもあるので、ボトムアップでは難しかったでしょう。
その前提で、なるべくスモールチームをつくり、リーダーを筆頭に“失敗が許される”現場環境をつくることが大事だと思います。先ほど近年の広告収入のグラフを紹介しましたが、当社でもさまざまな試行錯誤や失敗を繰り返し、2015年から少なくとも3年はビジネスをスケールできませんでした。その間を耐え、リーダーが率先して挑戦し転びながら、失敗の積み上げを許す環境を持てたことが今に結び付いていると思います。
中井
なるほど。とはいえ、掲げられていた「脱・旧雑誌広告営業」は簡単なことではないですよね。年単位でなかなか好転の兆しが見えず、社内に反対意見もあっただろうと思いますが、どう乗り越えたのですか?
長崎
実は、私も当初はそこまで課題を解像度高く捉えられていなかったところはあります。スイッチが入ったのは、ある年に新入社員から「10年後に僕らの仕事があるか」と聞かれたこと。そして、その話を伝えた上司に「お前はその仕事を与えることができるのか」と問われたことです。10年後に私自身は定年していても、次の世代にこの仕事をつなげないといけないのだと強烈に実感して、改革に身が入りました。
“わかりやすさ”の危険性を認識した上でデータに向き合う
中井
ありがとうございます。一方、篠田さんのお話では「ローカルこそデジタルと相性がいい」という指摘が意外でした。それはつまり、データを駆使すれば地域も国も越えられるから、これまでは無理だと思い込んでいたことを越えられる可能性が開けている、と。ローカルだからこそ、継続的な仕組みをつくりやすいというお話もありました。
篠田
その通りです。データやデジタルは垣根がないので、全国にユーザーがいるサービスから特定エリアのデータを絞り込んだ上で、地元に根差した精緻なデータ活用ができます。また、データに下支えされた「そのエリアならでは」という付加価値のあるコンテンツを提案することで、メディアの新収益へのトライアルにチャレンジしています。
また、地域における産学連携において、地元のテレビ局や新聞社の存在感は非常に大きいと実感しています。例えば福島では福島テレビと会津大学の共同プロジェクトとして「コロナ禍における会津若松市の新たな生活・観光スタイル」を分析し、情報バラエティ番組の中で放送しました。これは福島テレビが、その地域における様々なプレーヤー、オーディエンスをつなぐ「オーディエンスリレーション」の役割を果たしているからできたことです。

中井
今回、会場からご質問もいただいています。ビッグデータから人の気持ちや行動を導き出すことに可能性がありそうでも、どうやって自分たちのコンテンツや広告に生かせばよいのだろうか、と。篠田さんのようなデータサイエンティストと協業する場合、データやAIは現状では持っていないけれど「AIを使ってなにかできませんか」という依頼ってあり得るんでしょうか?
篠田
はい、実際そうした漠然とした依頼から始まることも多いです。もちろん、メディア企業自身がデータをいかに保有し活用するかという観点も大事ですが、高知放送の事例のようにすでに膨大なデータ量がある他社と組むことで、企画の幅は広がります。外部パートナーをうまく活用することは非常に有効だと思います。
中井
テレビ局だけでなく、新聞社ともお仕事をされていると思います。直近で、データジャーナリズムについても対談されていましたが、例えば英ガーディアン紙が取り組んでいるような「データでわかりやすく伝える」報道の形は今後も増えていくのでしょうか?
篠田
この場でデータジャーナリズムを語るのは恐縮ですが、私としては「報道の中立性を保った上で、生活者のリテラシーに委ねてデータを活用したインタラクティブなコンテンツを提供する」ことがデータジャーナリズムだと思っています。例えば難民の移動や、政府のお金の流れがどうなっているのか、個々の関心に合わせて図を触りながら情報を得られる。そのとき、わかりやすくつくるのは大事だとは思うものの、わかりやすさを最優先するならインタラクティブにする必要はないんですよね。データの見方も固定して「これが結論」と提示するのがいちばんわかりやすい。
でも、それはすごく危ないことだと思っています。データ活用で私もすごく気をつけているのですが、AIで何らかの結論まで出してしまうと、一元的なものの見方しか提示できず受けての考え方を狭めてしまったり、エッセンシャルなものが抜け落ちることがあると感じています。
なので、データで全てを明らかにわかりやすくすることが正解でもない。あくまで線引きが大事だと思います。新聞社なら例えばAIが記事を書くような場合、どこまでをAIで業務効率化し、どこからは人が書くべきだ、といった線引きが議論されることが重要なのではないかな、と。先ほどの講演タイトルを「データにできない想いはあるのか」としたのは、そんな考えを込めていました。
読者コミュニティ、地域コミュニティにこそ価値がある
中井
長崎さんが「脱・枠売り」を掲げ、デジタルを基点とする企画に取り組まれていることと、篠田さんが「データはコンテンツ開発に活用できる」と語られたことには共通点があると思いました。
篠田
その観点で私から長崎さんにうかがいたいのは、デジタルを基点にしようといっても年単位でなかなか成果が上がらない、その時期をどのように「待った」のだろうかと。社内をどう説得されたのでしょうか?
長崎
とにかく読者を見つけてくるので、3年間は待ってくれと、ひたすらレポートやプレゼンを繰り返していましたね。方針としては、やはり「読者に受けるものをつくる」ことに尽きます。読者の心を捉えることが最優先で、それだけを考える。
先ほどビジネス資産の見分けという話をしましたが、これまで我々は上2つの自社の価値だけを信じていたんですね。でも今は、下3つの読者コミュニティを認識しないといけない。この価値は読者の中にあるので、これまで以上に読者を知り、コミュニティの価値を増幅できる企画に注力していったんです。 それが広告価値の向上にも繋がると信じています。

篠田
とても興味深いです、先ほど紹介した「オーディエンスリレーション」の話に重なりました。ローカルメディアが地元の各プレーヤーとの関係構築に価値を見いだすことで、継続的な取り組みが可能になる。そして、データはそのつないだコミュニティを下支えし、活性化していくことができると考えています。
長崎
同感です。我々も、デジタル広告のうち約半分はプラットフォーマーを介した運用型広告の収入ですが、同時にコンテンツや読者コミュニティに基づいた企画を大事にしていかなければいけないと考えています。デジタル基点のクリエイティブであり、エンターテインメントを提供することが、プラットフォーマーとの付き合い方であり対抗軸になると考えています。
その点で、篠田さんのお話には多くの示唆がありました。AIで単に広告の効率を高めるより、「AIでカレーをつくる」ほうが断然ワクワクしますよね。やはり、AIやデータをいかにコンテンツとひもづけるか、クリエイティブとデータサイエンスをどう結びつけるかにヒントがあると実感しました。特にエリア密着のローカルメディアでは、おもしろい切り口でのデータ活用をたくさん考え得ると思います。
篠田
そんなふうに言っていただけて、光栄の極みですね。
中井
広告会社やメディアビジネスのDXを推進する上では、デジタル環境を前提にクリエイティブ力を発揮するという観点が欠かせませんね。特に、地域ならではの示唆も多くいただきました。お二人とも、貴重なお話をありがとうございました。

長崎 亘宏 氏
株式会社講談社
ライツ・メディアビジネス局 局次長 兼 メディア開発部 部長
広告会社でのメディアプランニング職を経て、2006年 講談社に入社。広告営業と企画開発を担当。2010年より、雑誌広告効果測定調査「M-VALUE」設立・運営に従事。2014年より、JIAAネイティブ広告部会座長として、ガイドラインや広告効果指標を整備。2017年より、日本ABC協会雑誌ブランド指標ワーキンググループのリーダーとしてメディアデータの再編に従事。

篠田 裕之
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ
メディアビジネス基盤開発局
データサイエンティスト。自動車、通信、教育、など様々な業界のビッグデータを活用したマーケティングを手掛ける一方、観光、スポーツに関するデータビジュアライズを行う。近年は人間の味の好みに基づいたソリューション開発や、脳波を活用したマーケティングのリサーチに携わる。































