コラム
多様性の現在地
~ジェンダーから、ジェネレーションへ~
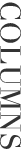

リアル・イベントとオンラインを融合したハイブリッド形式で開催されたアドバタイジングウィーク・アジア2022。リアルとバーチャルの融合によりこれまで以上に参加の機会を広げ、「マーケティング、メディア、テクノロジー、クリエイティブなどの業界をひとつにし、変化を推進していくこと」を視座に、さまざまなセッションやネットワーキングが展開されました。
本稿では、株式会社講談社C-stationチーフエディターである前田亮氏の進行のもと、著述家、メディアプロデューサーの羽生祥子氏、博報堂DYメディアパートナーズの森永真弓が、多様性=ダイバーシティの実現を阻む課題に踏み込みながら、その解決の糸口を探ったセッションの様子をご紹介します。
前田 亮
C-stationチーフエディター
株式会社講談社
羽生 祥子
著述家、メディアプロデューサー
森永 真弓
メディア環境研究所 上席研究員
博報堂DYメディアパートナーズ
■多くの組織でジェンダーバランスの悪い状態が維持されている
前田
私は講談社で長らく女性誌の編集長を務めた後、現在C-stationという、社会課題解決を目指すBtoBサイトの運営を行っています。まずはメディア業界におけるジェンダーバランスの現状についてお話しします。女性が社長を務める民放テレビ局は127社のうち1社。民放ラジオ局は98社のうち1社です。弊社も役員17名のうち女性は1人で、とてもジェンダーバランスが整っているとはいえません。

羽生
私が長らく在籍してきた日経BPでは、社長会長除いて10人いる役員のうち女性は2人。一般的に見ても20%というのは多い方だと思いますが、それも私のような人間が編集長という立場で、口うるさく働きかけを行ってきたからかなと思います。
私は2013年に、働くママパパ向けのメディア「日経DUAL」を立ち上げましたが、いまほどデジタルメディアが主流ではない時代に、出産を終えたばかりの女性の記者たちをどう回していくか非常に頭を悩ませました。最初に取り組んだのは、在宅でも“公開ボタン”を押せるような、CMSの環境を整えることでした。彼女たちは17時半に保育園のお迎えがあり、その後子どもをお風呂に入れたり寝かしつけたりと21時くらいまではファミリータイムになりますが、その後の時間を活用すれば、たとえ23時59分までに校了というケースでもリモート対応できるわけです。そうして世間に先駆けてリモートワークの体制を築き、以後10年間、いかに無事故無違反で校了まで終えられるかの勝負を続けてきました。そのおかげでコロナ禍の際も慌てることはありませんでしたね。
森永
私が所属する博報堂DYメディアパートナーズにおいては女性の役員は現在ゼロで、グループ全体で何人かいる程度です。
私は2000年代前半からずっとデジタルマーケティングにかかわってきましたが、研修や人材募集という段になると、集まってくるのは理系出身の男性が圧倒的で、講師である自分以外は全員男性という場面も珍しくありませんでした。
前田
なぜ組織にジェンダーの多様性が必要で、どうすればそれを実現できるとお考えですか。
羽生
メディアに限らず、多くの会社組織では偽女性活躍組織・男性同化型タイプと、戦力外組織に二極化しているように思います。前者は、いわゆるロール(役割)=大きい声で高圧的に回していく、ルール(約束)=上司から指示されれば24時間可能な限りどこへでも馳せ参じる、ツール(道具)=ゴルフ接待や女性のいるお店に連れていくなど……これらすべてに同化できる人だけが活躍する組織。それができない人は後者の戦力外とみなされ、数字を持たない部署にいくというのが現状だと思っています。
森永
こういう話題で男女を対立構造で見てしまうと話がややこしくなるしもったいないですよね。よく「女性は役職につきたがらない」などの声もありますが、男性だってそういう方はいるはずです。同じように体育会系のノリ、ゴルフや接待が苦手だという男性もいるでしょうし、羽生さんが確立されたリモートワーク体制のおかげで助かった男性もいたと思う。逆にいま権力を持つ男性が持つ悩みや生きづらさを、女性がくみ取ることもできると思います。
■多様性があるからこそ、不測の事態に備え中長期的な成長を遂げることができる
前田
羽生さんは今年1月に上梓された『SDGs、ESG経営に必須! 多様性って何ですか?D&I、ジェンダー平等入門』(日経BP)という本で、なぜ組織に多様性が必要なのか、そのために何から進めるべきなのかをデータや実例に基づいてまとめられています。多様性に必要な視点をご説明いただけますか。
羽生
ダイバーシティを考える際に必要な視点として、性別、年齢、民族、宗教など属性の多様性と、理系か文系か、営業に向き不向き、挑戦的か保守的かといった特性の多様性があります。この、属性と特性を1対1で結び付けてしまうことが、いま特に問題視されているのです。ESG経営やSDGsの観点においてそうした発言がNGである理由は、多くの日本企業のように「男性」という1枚のカードでしか戦えない単一文化の組織では、中長期的な成長が見込めないからです。カードコレクターゲームで例えるなら、いま必要なのはさまざまな属性がそろった魅力的で最強のデッキ。炎タイプだけではなく、水、風、魔法など異なる強みを持つカードを集めることで、予期せぬ事態にも対応できる体制ができる。そうして初めて組織は中長期的に伸びるんです。
森永
実際、就職の際に、事務職を希望する男性も結構いるのではないかと思うんですが、それを選べない現状がありますよね。入社後は、出世に向かってまい進しない限り低評価を受ける。正直とても生きづらい文化だと思います。ひとつの価値観に我慢して従うのがこれまでの文化だったとすると、社内でも業界でも多様性を持たせることで、いろんな職業や働き方の選択肢が増え、ひいては自由で多彩な生き方の実現にもつながるのではないかと思います。
■コンテンツメーカーは世代間の認識のズレに危機感を覚えるべき
前田
森永さんはコンテンツファンの動向にお詳しいですが、スポーツと世代についてのお考えを教えてください。
森永
コンテンツファンは非常に多彩です。以前ビジュアル系バンドの10代20代の女性ファンを調査したところ、あまりにも80年代カルチャーに詳しいのに驚きました。もともとレジェンドとして尊敬していた80年代のビジュアル系バンドの上の世代のファンと交流するうち、周辺のカルチャーについてもいろいろと教わったそうです。韓流ファンなら、上の世代が下の若い世代にひっぱられるといったことが起きているかもしれません。つまりジェネレーションでコンテンツファンを区切ることにはもはやあまり意味がなくて、興味関心で切っていくことで、実は同じ意識を持つ集団の姿が見えてくるんです。たとえばサッカーは、以前は若い世代のファンに支えられているイメージでしたが、実は若い人の流入が少なく、毎年ファンの年齢層が少しずつ上がっています。一方で野球は、なんとなく年齢層の高い人が観るスポーツだと思われていますが、実は男女ともに若い“見る専”のファンがたくさん入ってきている。世代に対する無意識の思い込みが、かえってジェネレーションの多様性を見えなくしていると思います。
ちなみに25歳以下をZ世代とまとめてしまうことにも違和感を覚えます。世代でくくることは楽ですが、あえてそうしないことが、多様性や変化やイノベーションの推進につながるのではないでしょうか。私たちのマインドセットの更新も問われているのだと思います。
前田
ではいまの若い世代に対して、どんなことを感じていますか。
森永
最近『欲望で捉えるデジタルマーケティング史』(太田出版)という、インターネットの歴史を語る本を書いたのですが、それを読んだ若い方から、「最初は自分の知らない歴史の話として読んでいたが、次第にこの歴史の中に自分がいると感じた。点だったものが線として見え、その流れのうえにいまの自分たちがいると理解できた」という感想をいただきました。上の世代の話が若者に嫌われるのは、もしかしたら点として聞こえているからかもしれない。線としてつながるよう伝えることで、経験値をうまく提供できるのではないかと思いました。

またマーケティング調査でよくある「SNSをよく使いますか?」という質問にも少しズレを感じます。若者はつねにSNSを起点とし、そこからテレビ番組をチェックしたりニュースを見たり雑誌などメディアを購入したりしている。SNSは、ほかのメディアと同じレベル上で比較するものではなく、すでに彼らの生活基盤なんです。ベースである以上SNSの利用が活発なのは当然であって、可処分時間からSNSの時間をどう割くかという思考回路では本質を捉えられない。マーケティングデータの把握の限界を感じるところでもあります。
羽生
そうした認識のズレは、価値観、仕事観、家族観、経済観にも生じてきていますよね。経済成長は当たり前で企業は前年度比135%を目指すべきとか、週休3日は休みすぎだとか、そういう考えに固執し若い世代と感覚がずれていくことに対し、コンテンツメーカーであるメディアはもっと危機感を持つべきだと思います。
■一時期の不快感や衝突、効率の悪さを超えたところに革新と成長がある
羽生
もしひとつのロールモデルに固執してそれに同化させようとしていけば、人材は偏っていきます。またリスク盲点があったり、失敗への恐怖から、イノベーターの孤立も招いてしまうでしょう。でも適度に異なる特性の人材が散らばっていれば、ある意味カオスで不快感や衝突も生じるでしょうが、イノベーターも力を発揮できて組織の革新や成長につながります。パーパスやビジョンによる求心力でこの全体をまとめ、成長していかなければならないと思います。

森永
仕事でも、たとえば全員がそうだねといってすぐ合意するチームの場合、なぜ別の意見、視点が出ないかを問う癖をつけたほうがいいですね。その点リーダーの資質も重要になってくると思います。
羽生
いまの日本は男性対女性の議論でかれこれ20年くらい足踏みをしている状態。でも1枚のカードすら切れない組織が、ほかの重要なカードを切れますかと問いたい。ジェネレーションの面で新しいルールや組織のモノサシを採用することなどから、新たな一歩を踏み出すときなのではないかと思います。
森永
多様性を取り入れると一瞬だけ効率が悪くなるということも覚えておくべきです。多様性をもってイノベーティブでクリエイティブな組織に変わるためには、少しの我慢が必要。そのうえで、いま権力を持つ側が、ちょっと相手に譲ってみることが大事だと思います。
前田
お2人ともありがとうございました。

前田 亮
C-stationチーフエディター
株式会社講談社
1986年講談社に入社。女性誌部門に配属され、with、ViViなど複数のメディアで、長く女性誌編集に携わる。2009年からwith編集長を務めたのち、2012年デジタル部門に異動。電子雑誌の草創期の整えに参画。2017年、メディア部門に異動。現在はライツ・メディアビジネス局メディア開発部に所属。BtoBサイト「C-station」「講談社SDGs by C-station」のチーフエディター。

羽生 祥子
著述家、メディアプロデューサー
2000年に京都大学卒業後、渡仏。帰国後、02年編集工学研究所で松岡正剛に師事し「千夜千冊」に関わる。05年現日経BP入社。12年「日経マネー」副編集長、13年「日経DUAL」創刊編集長、18年「日経xwoman」創刊編集長。内閣府少子化対策大綱検討会、厚生労働省イクメンプロジェクト委員など歴任。京都大学等で講義、企業研修、TV等出演多数。著書に『多様性って何ですか?D&I、ジェンダー平等入門』(日経BP)。

森永 真弓
メディア環境研究所 上席研究員
博報堂DYメディアパートナーズ
通信会社を経て博報堂に入社し現在に至る。 コンテンツやコミュニケーションの名脇役としてのデジタル活用を構想構築する裏方請負人。 テクノロジー、ネットヘビーユーザー、オタク文化研究などをテーマにしたメディア出演や執筆活動も行っている。自称「なけなしの精神力でコミュ障を打開する引きこもらない方のオタク」。 WOMマーケティング協議会理事。共著に「グルメサイトで★★★(ホシ3つ)の店は、本当に美味しいのか」(マガジンハウス)がある。































