コラム
Media Innovation Lab
「オーディエンスアクションビジネス」という新たな挑戦──メディアイノベーションラボ新春座談会【Media Innovation Labレポート46】
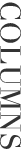

メディアビジネスやコンテンツビジネスの情報収集と発信を続けているメディアイノベーションラボ恒例の新春対談が今年も行われました。博報堂DYメディアパートナーズの代表取締役社長である矢嶋弘毅と、2024年に立ち上げられた「オーディエンスアクションビジネス」の部門リーダーである笠置淳行が、今年から始まる博報堂DYグループの新しい挑戦について語り合いました。
矢嶋 弘毅
博報堂DYメディアパートナーズ
代表取締役社長
笠置 淳行
博報堂DYメディアパートナーズ
テレビラジオBD局 局長
聞き手:田代 奈美
博報堂DYメディアパートナーズ
ナレッジイノベーション局 局長 兼 メディア環境研究所 所長 兼 Media Innovation Lab リーダー
高騰するコンテンツのコストにいかに対応するか
田代
日本、米シリコンバレー、中国に拠点を置いて、メディアビジネスの最前線の情報収集と情報発信を行ってきたメディアイノベーションラボの活動も今年で6年目となります。年初に開催している新春対談も恒例となりました。今回は、博報堂DYグループが新たに掲げた「オーディエンスアクションビジネス」をテーマに、お二人のお話を伺っていきたいと思います。はじめに、2024年のメディアやコンテンツの動向を振り返っていただけますか。
矢嶋
2024年は、スポーツが盛り上がった1年でしたね。世界規模のスポーツイベントがあり、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手の活躍も大きな注目を集めました。国内では、Bリーグの観客動員数が過去最多を記録しています。
一方、戦国時代の日本を描いたテレビドラマ『SHOGUN 将軍』が、米テレビ界のアカデミー賞と言われるエミー賞で、過去最多となる18部門受賞という快挙を成し遂げました。またゴールデングローブ賞でも、作品賞、主演男優賞など4つの賞を受賞しています。この作品は動画プラットフォームで配信されました。今後、プラットフォームのコンテンツはさらに充実していくと思います。
もう1つ、スマートフォンで視聴する縦型ショートドラマに日本の放送局が本格的に取り組み始めたのも、2024年の大きな動きでした。
笠置
アメリカや中国では、お金を払ってショートドラマを見るスタイルが定着しています。日本ではマンガアプリの課金モデルは普及していますが、ショートドラマにお金を払う文化はこれまであまりありませんでした。しかし、昨年からショートドラマの課金モデルも徐々に広がってきています。マンガに続くビッグコンテンツになる可能性も大いにあると思います。
スポーツもかなり盛り上がりましたが、一方で放映権料が世界的に高騰した年でもありました。そのため、人気のあるスポーツの試合でも、放送局が地上波での放送を見送るケースが出てきています。スポーツ放映をみんなでを楽しむというこれまでのスタイルを維持していくには、新しいビジネスモデルが必要になっていると感じます。
矢嶋
スポーツに限らず、膨大な製作費や放映権料が必要となるビッグコンテンツは、従来の広告モデルだけで放映することが難しくなりつつあります。
映画製作では、コンテンツの二次利用、三次利用によって製作費を回収していくモデルが定着しています。テレビコンテンツも、広告モデルによる放映に加えて、プラットフォームでの有料配信などを前提とした複合的なモデルにシフトしていかざるを得ないと思います。これは放送局の力が弱まっているということではありません。優れたコンテンツをつくるにはお金がかかる時代になっているということです。

メディアの新しい収益モデル
田代
博報堂DYメディアパートナーズのメディア環境研究所の調査結果を見ると、若年層になるほど、必要な情報やコンテンツにはお金を払ってもいいと考えている様です。広告だけではなく、直接的な課金などによってコンテンツの質を保っていくというのが時代の趨勢と言えるかもしれません。そういった変化に対応する新しいビジネスモデルが「オーディエンスアクションビジネス」です。このモデルの考え方をご説明いただけますか。
笠置
従来、コンテンツの放映や配信は一方通行でした。メディアから生活者にコンテンツを届けるという方向しかなかったわけです。しかし最近では、生活者がほしいコンテンツにお金を払ったり、YouTuberに「投げ銭」を送ったりすることが簡単にできる仕組みが多数開発されています。そこにビジネスチャンスを見出そうというのが、オーディエンスアクションビジネスの基本的な考え方です。
オーディエンスアクションビジネスに必要とされるのは、3つの要素であると私たちは考えています。オーディエンスの「熱狂」を生む優れたコンテンツ、オーディエンスの行動を促す戦略、そして、継続性と成長可能性のあるビジネスを成立させる仕組みづくり。その3つです。
田代
昔からある通販番組なども、オーディエンスに行動を促すコンテンツでした。そういった従来型のコンテンツビジネスと、オーディエンスアクションビジネスの違いはどういった点にあるのでしょうか。
矢嶋
これまでの広告会社の役割は、メディアに接している人たちに広告の力でメッセージを届けたり、アクションを促したりすることでした。その目的は、クライアントのビジネスを成功に導くことです。通販番組なら、その番組のスポンサー企業の商品を買ってもらうことが必要でした。メディアを活用してクライアントに貢献すること。それが広告会社の仕事だったわけです。
しかし、博報堂DYグループは、クライアントのパートナーであるばかりではなく、メディアやコンテンツプロバイダーのパートナーでもあります。メディアが十分な収益を上げられなければ、広告そのものが成り立たなくなってしまう。だから僕たちは、引き続き広告ビジネスでクライアントに貢献する一方で、メディアにも貢献しなければなりません。広告ビジネス以外の収益モデルによって、メディアの成長に寄与すること。それをオーディエンスアクションビジネスと呼びたいと僕は思っています。これはこれまでにはなかった新しい領域のビジネスです。
笠置
メディアの数が増え、生活者のメディア接触が多様化する中で、それぞれのメディアが成長モデルを考え直さなければならなくなっています。例えば、従来のテレビの成功の方程式は「視聴率を上げる」ことでした。しかし、その単一モデルだけでは他のメディアに対抗できなくなりつつあります。これは、テレビ以外のメディアにも言えることです。オーディエンスアクションビジネスは、そのような変化に対応するビジネスを創り出していくことだと考えています。
オーディエンスアクションビジネスの3つの領域
田代
オーディエンスアクションビジネスには、3つの領域があると矢嶋さんはおっしゃっています。そのそれぞれについてご説明いただけますか。
矢嶋
1つが、すでに大きな市場になってきているペイ・パー・ビューやサブスクリプションです。コンテンツに対して直接お金を払う仕組みですね。2つ目が、いわゆる「ショッパブルコンテンツ」です。インターネットにつながったコネクテッドテレビやスマートフォンなどでコンテンツを見て、そこからダイレクトに商品やサービスを購入できる仕組みです。コンテンツを楽しみながら、そこに出てくる商品を買いたいという要求に応えられる比較的新しいモデルです。
田代
ショッパブルはこれから伸びていく領域ですよね。アメリカでは様々な施策が生まれてきている様ですが、ショッパブルで購買した経験のある人はまだ2割程度と聞きます。
笠置
ドラマに出演している俳優が着ている服が売れるといった現象は、以前からありました。昔はリアルショップに足を運んで買わなければならなかったものが、現在ではコンテンツを見ながらインターネットでダイレクトに変えるようになった。そう考えれば、コンテンツに連動したショッパブル領域は今後どんどん成長していく可能性があると考えられます。

重要なのは、UI/UXの工夫だと思います。例えば、インターネットにつながっていないモニターでも、スマホで商品の写真を撮れば購入できるといったやり方を行うユーザーがアメリカでは増えつつあるそうです。いかに購買というアクションにつながりやすいインターフェースをつくれるか。そこに工夫の余地があると思います。
田代
3つ目の領域についてもお聞かせください。
矢嶋
スポーツの試合の勝敗予測をビジネス化するモデル、いわゆるスポーツベッティングです。先ほど話に出たように、スポーツの放映権料は年々上がっています。今後、広告収入だけでは放映できないスポーツコンテンツがますます増えていくでしょう。広告、ペイ・パー・ビュー、そしてスポーツベッティング。この3本柱で良質なコンテンツを確保していくという流れになっていくと考えられます。
笠置
多くの人が気軽にスポーツコンテンツを楽しめるようにするには、新しいモデルが必要ということですよね。世界的に見れば、その選択肢の1つがベッティングであることは確かです。日本では、スポーツの勝敗予測にお金を賭けることにはまだまだ敬遠する向きもあります。そういった文化を踏まえながら、できることがないかを模索していくことが僕たちの役割だと思います。
矢嶋
欧米のようなベッティングビジネスをすぐに立ち上げることは日本では難しいですよね。しかし、環境が整ってから準備を始めたら出遅れてしまいます。実現可能性を探りながら、ナレッジを蓄積していくことが必要です。
「攻め」のツールとしてのAI
田代
広告ビジネスや従来型のメディアビジネスを得意としてきた博報堂DYグループにとって、新しいビジネスモデルに挑戦するのはたいへんなことです。しかし、やりがいも大いにあると感じます。
矢嶋
「どちらがたいへんだろうか」と考えるべきだと僕は思っています。これまでのビジネスモデルにこだわって、そこで踏ん張っていくことと、これから成長する可能性のある市場にチャレンジしていくこと。そのどちらがたいへんだと思いますか?
田代
「耐える」ことと「攻める」ことの違いということですね。どちらもたいへんですが、攻める方がワクワクしますよね。

矢嶋
僕もそう思います。新しいビジネスモデルに挑戦すると言っても、五里霧中の中でやみくもにチャレンジするわけではありません。あくまでも、コンテンツビジネス、あるいはメディアビジネスという枠の中での挑戦です。
歴史を見れば、コンテンツと広告の関係において先にあるのは常にコンテンツです。まずコンテンツがあって、その経済モデルを成立させるために広告が力を発揮する。そういう順番でした。だから、コンテンツの収益モデルが安定しなければ、広告モデルも成立しないわけです。
これまでは、広告費によってコンテンツの製作や調達を賄うモデルがワークしていました。しかし繰り返すように、コンテンツのコストが高騰すれば、広告費だけで良質なコンテンツを生活者に届けることは難しくなります。メディアやコンテンツホルダーが広告以外の収益源を必要としているときに、そのパートナーである僕たちが手をこまねいているという選択肢はありません。だからこそ、新しいチャレンジが必要である。僕はそう思っています。
田代
新しいビジネスモデルに挑戦するにあたっては、AIも重要なツールになりそうですね。
笠置
オーディエンスアクションビジネスのいろいろな場面でAIの力が生かされていくことになると思います。業務のインフラになることはもちろん、新しい価値を生み出していくためのエンジンになるのがAIです。シリコンバレーでは、数年前からAIが主要な投資領域になっています。僕たちもAIへの投資を惜しむべきではないと思います。
矢嶋
AIには、ビジネスへの参入障壁を下げる力があります。それは僕たちにとってチャンスであり、また脅威でもあります。AIのクリエイティビティはどんどん進化していて、その力を使って独創的なコンテンツを生み出すことができるようになっている。これは、これからコンテンツビジネスの新しい領域に挑戦しようとしている僕たちにとって大きな力となるでしょう。
一方、広告クリエイティブにもAIが使えるようになっていると考えれば、広告ビジネスという僕たちのこれまでの本業への参入障壁も下がっているということになります。僕たちは、AIを使って攻めていくこともできるし、AIを使うほかのプレーヤーから攻められる立場でもある。そのことを肝に銘じておくべきだと思います。
新たなチャレンジのスタートの年に
田代
これまで別々の会社だった博報堂と博報堂DYメディアパートナーズは、今年の4月に統合することになりました。こちらについてもお話いただけますか。
矢嶋
博報堂と博報堂DYメディアパートナーズが別会社になったのは2003年でした。それから20年以上が経って、企業、メディア、コンテンツビジネスを取り巻く環境は大きく変わりました。その変化に、クライアントとメディアの両者のパートナーである博報堂DYグループはどう対応していけばいいか──。その問いに対する答えが、再統合でした。
今後、僕たちのビジネスにおいて最も重要になるのは、データドリブンマーケティングとコンテンツドリブンマーケティングです。多岐にわたるデータをトータルに活用すること。そしてメディアやコンテンツプロバイダーとともに良質なコンテンツを生活者に届けていくこと。それはいずれも総力戦になります。これまで別々だったオペレーション、クリエーション、マーケティングを統合し、博報堂DYグループの力を最大化する。それによって、クライアント、メディア、生活者にこれまで以上に貢献していく。そのための統合であるとご理解いただければと思います。
田代
最後に、これからのオーディエンスアクションビジネスにかける思いをお聞かせください。
笠置
2024年は、オーディエンスアクションビジネスの基盤をつくる年でした。今年からは、いよいよ収益モデルを確立していくフェーズに入っていきます。矢嶋さんからは、「大きなホームランを打て」と言われています(笑)。まずはこつこつ安打を積み重ねて、数年後には大きなホームランが打てる体制をつくっていきたいと考えています。
矢嶋
新しい市場でビジネスを成立させるのは時間がかかるものです。時間をかけすぎてはいけませんが、焦る必要もないと思っています。広告ビジネス、メディアビジネスを引き続き強化しながら、新しい領域へのチャレンジに邁進していく。その本格的なスタートになる年が2025年です。オーディエンスアクションビジネスを1つの柱に育てながら、博報堂DYグループをさらに大きく進化させていきたい。そう思っています。


※Media Innovation Lab (メディアイノベーションラボ)
博報堂DYメディアパートナーズとHakuhodo DY ONEが、日本、シリコンバレー、アセアンを活動拠点とし、AdX(アド・トランスフォーメーション)をテーマにイノベーション創出に向けた情報収集や分析、発信を行う専門組織。両社の力を統合し、メディアビジネス・デジタル領域における次世代ビジネス開発に向けたメディア産業の新たな可能性を模索していきます。

矢嶋 弘毅
博報堂DYメディアパートナーズ
代表取締役社長

笠置 淳行
博報堂DYメディアパートナーズ
テレビラジオBD局 局長

田代 奈美
博報堂DYメディアパートナーズ
ナレッジイノベーション局 局長 兼 メディア環境研究所 所長 兼 Media Innovation Lab リーダー































