コラム
データドリブン
「決定された未来はない」新たなテクノロジーに対峙したとき、 私たちは考えることを止めてはいけない【データ・クリエイティブ対談 第3弾】(後編)~ゲスト:久保田晃弘先生
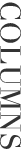
データ・クリエイティブの進化の在り方について、博報堂DYグループ社員と識者が語り合う『データ・クリエイティブ対談』。第3弾のゲストは、多摩美術大学の久保田晃弘先生です。前編では、データから導き出された結果を、仮説ではなく結論であると人々が捉えがちであることに警鐘を鳴らしました。後編では、フィクションの持つ可能性に言及しつつ、データにどう向き合うべきかについて、より深く議論をしていきます。聞き手は博報堂DYメディアパートナーズの篠田裕之です。

自ら作ることによって技術を我々の手に取り戻す
久保田:メディアを考えようとするとき、メディアを作ってみることが大事だと思います。あるメディアを購入したり、使用するだけではなく、シンプルなものでもいいので、自分で作ってみることで、それで何ができて何ができないかが、だんだん分かってくるようになります。“作る”という行為は、必然的に双方向的なので、“見る(考える)”こととはどういうことなのかを考えるためにも非常に重要です。
篠田:作れるくらいの粒度で物を見ることで、見る粒度も高まるということですね。
久保田:ええ、例えば食事も同じですよね。レストランに行って食べるだけじゃなく、それが何を素材にしているのかを考えて、その一部でもいいから自分で作ってみることで、料理に対する理解が深まっていきます。プログラミングやデータ、そしてAIについても同様です。その多くがオープンソースとして提供されているので、実際に作ることができます。
篠田:メディアアートの価値には、インタラクティブ性のほかにノンフィクション性や粒度の高さがあると思いました。作品を作ってみることで、映像作品として示すといったフィクションの世界から、「こういうテクノロジーを作ったら、こういうことができてしまいますよね」というノンフィクションになる。そういう粒度の高さによって、議論を深めることができると思います。

久保田:前回対談されていた長谷川愛さんの活動が重要だと思っているのは、現実を忘れたり覆い隠すためのフィクションではなく、「今ここ」を考えるためのフィクションの可能性を提示しているからです。未来予測をすることは、簡単といえば簡単です。誰も検証できないし、検証できたときにはそれが未来でなくなっているから意味がない。今にとっても、未来にとっても無駄なものです。それよりも、その未来予測を求め、生み出すプロセスを議論することの方が重要です。
一体「今ここで何が起こっているのか」という話を抜きにして、未来予測もないと思うんです。インターネット上のビッグデータがどのように管理されているかという、その仕組みを問われても多くの人が答えられない。それなのになぜ未来予測ができるのかということです。だから、まずは「今ここで何が起こっているのか」を考えなければなりません。でもそれがいちばん難しい。
何かしらの理論を勉強することとは異なり、長谷川さんも取り組んでいるスペキュラティブデザインのような、現実と異なるフィクションを持ってくることで、技術の中に潜む人間の願望を浮き彫りにしていく思考です。願望や欲望の多くは、往々にして無意識下にあるものだから、対峙されるようなフィクションがないかぎり、なかなか表に浮かび上がってくることはないでしょう。
逆に言えば、データサイエンスから導かれるものもフィクションだと言えます。人間から切り離されたデータから生み出される結果は、それ自身が導き出されたプロセスがブラックボックスであるかぎり、フィクションでしかありません。その役割はたくさんありますが、未来予測のようなフィクションが現実であるかのように信じて、その通りに行動しようとするのは、全体主義的な社会の動きにつながっていく点で危険だと思います。
例えば、機械学習に用いられるデータはすべて過去のものです。つまり、そこには過去の過ちや至らなさがデータ化されていて、データそのものに埋め込まれていた偏見や誤解が、その結果に表れてきます。だとすれば、そのことを逆に利用しなければなりません。機械学習によって、人間の過去の過ちや偏見を顕在化させ、今の行動に反映させることが、クリエイティビティにつながっていきます。本当に、技術は使い方次第なんです。データも人間が作ったもの。諦めたらおしまいです。
政治でも何でもいいのですが、影響力や権力などの“力”を手に入れたい人たちは、多くの人に自分の言いなりになってほしいわけです。粘りに粘って考え抜く、なんていうことは絶対にやめてほしい。効率性や有用性、そして生産性といった言葉が、人を考えさせないためによく使われます。そこがエンジニアリングの怖いところです。でも、それは今に始まったことではなく、そういった口実のもとに考えることをやめさせてきたことは、これまでの歴史の中でもずっと起きてきたわけです。
篠田:久保田先生の過去のインタビューで、テクノロジーが民主化してからがすごく面白いとおっしゃっていたと思います。そういうことが、今の話とつながると思います。
久保田:今日のデジタル・テクノロジーは、ますますエリートだけのものになっています。そして「僕らは作る人、あなたは使う人」と分けようとしています。でも、たった10行のプログラムでも、実際に自分で作ることで、こんなことができる(行われている)と少しずつ気がついていく。民主化とは、そういうことなのだと思います。

データについて考えることは、数を定義することに繋がる
篠田:福岡伸一の『生物と無生物のあいだ』という本で触れられていたことですが、人間ではないものを、徐々に人間へ近づけて作っていったとき、「どこから我々が人間らしさを認めるのか」という議論があります。バイオアートの意義は、例えば、このような議論を起こし、その議論自体が人間らしさを生む、ということなのかもしれません。
久保田:例えば、「フランケンシュタインとは一体何なのか?」という話もそうですね。そこには、なぜフランケンシュタインが男なのか、なぜあのように醜くなければならなかったのかといったさまざまな問題が含まれています。でも、女性で美しいフランケンシュタインだったらみんな喜ぶの? みたいな話にしてしまうと、またそれも違うわけです。
分かりやすさも効率性のひとつで、「一言で伝わる」というのは一見良さそうに聞こえますが、分からないのに分かった気にさせるという意味で、危険なことでもあるわけです。巷に溢れる陰謀論が、まさにそのいい例です。分かりやすさには、いろいろなスパンやグラデーションがあるので、単に分かればいいのではなく、分かることによって次の分からなさに気づくためにも、常に丁寧な言い方をしないといけないですよね。分かりやすさには、暴力と同じ側面もあるのです。
篠田:『フランケンシュタイン』の人造人間は、差別のメタファーでもあったと思います。醜い男性という描写がその暗喩であると。テクノロジーに内在するテーマを、どういう表現で伝えるべきかを考えるのは非常に興味深いと思います。
久保田:そうですね。『フランケンシュタイン』は、メアリー・シェリーという、まだ20歳の若い女性が書いた作品でしたが、電気を生命の起源として捉えていた当時のテクノロジーを反映した小説だともいわれています。このような作品を通して、自然現象や技術を当時の市民がどう受容していたかも分かります。それに、フランケンシュタイン博士が雷によって人造人間を稼働させたときに、「私は神になった気がした(Oh, in the name of God! Now I know what it feels like to be God!)」と言ったことは象徴的です。神は全能であり、まだダーウィンは進化論を発見してはいませんでした。ひとつのフィクションではありますが、その中に人間や社会のさまざまな要素がたたみ込まれています。人間がつくった技術こそが、ひとつのフィクションでもあるのです。
篠田:最近、マリオ・リヴィオの『神は数学者か?──数学の不可思議な歴史』という本を読んですごく面白いと思ったのは、「数字は発明なのか、発見なのか」という議論があったことです。テクノロジーについても、それが生まれたとき、テクニカルな意味では“発明”だと思いますが、自然現象や人間が本来持っている欲望や意識を“発見”したとも解釈できると思います。

久保田:はい。僕もそう思います。エドワード・フレンケルの「ラングランズ・プログラム」という数学の統一理論を探求している数学者が、NHKの番組で「数学はどこまで普遍的か?」という話をしていました。数は人間が発見したという言い方もできるけれど、自然数のようなものは、人間でなくても物質があるかぎり、普遍的に存在するものだと言っていました。
僕らは無意識に2+3=5だと理解しているけれども、モノと結びついた自然数、例えばゼロや負の数、小数や無理数などは、どこまでが普遍的で、どこからが人間だけのものなのか気になりますよね。「数とはこういうものだ」という数学基礎論的な理解に達しなくても、なぜ僕らはこの数を何となく学校で教わった通りに、−2×−2=4だと無意識に受け入れているのか、とか。そもそも数とは何なのかを考えることで、非人間の世界を想像したり、または議論できるようになるはずです。
篠田:数にはスピリチュアルな側面と実際的な側面があり、その間を行き来できることが人に興味を持たせる点なのだと思います。
もうひとつ思ったのが、数自体、人間が発明したものだという側面があるとして、もし地球が滅びて、新しく生まれ変わったとき、今とまったく同じような数の概念になるのかという話もあると思います。
さまざまな要因で数の概念が変わるとするなら、先ほどのAIに学習させるデータ自体の偏りの問題に近い議論になります。つまりデータとは、数をどこでカウントしたり、どう捉えるかによって、その意味が変わってきます。数の概念まで立ち戻らずとも、身近な例では、YouTubeや音楽プレーヤーの再生回数の場合、全部再生し終えた段階で再生回数を1にするのか、10秒流れたら1とカウントするのか、0秒であっても再生ボタンをクリックした瞬間に1とカウントするのか、によって結果が異なる。もちろんAIに学習させた場合も、まったく違う結果が出てきます。
久保田:本当にそうですね。再生回数の仕組みを知れば、botで再生回数を人為的に増やすこともできる。それは人間が作った技術から導かれる、ある種の論理的帰結でもあるわけです。そういうことも含めて、技術に対して人間はどういうことをやってしまうかを考えてみれば、技術の意味はどんどん深まっていくでしょうね。

篠田:実際にYouTubeでも、そういうbotが流行りすぎたので、上位表示するためのアルゴリズムから再生回数の重要度を下げて、総視聴時間と再生維持率を重視しています。つまり、瞬間再生してはリローディングすることは、むしろマイナス効果で、まったく興味が持たれていない動画として下の方に表示されてしまいます。テクノロジーと人間の特性の関係を踏まえて、数の意味を捉え直したということだと思います。
久保田:データの量やその処理速度が人間の感覚を超えて増大したことで、今は危険な程に、データとその処理がどんどん複雑になって見えなくなっています。そのことを無邪気に肯定するのか、批判的に思索するのかで、まず大きく別れるでしょうね。
今『ニュー・ダーク・エイジ テクノロジーと未来についての10の考察』という本を翻訳しています(※)。この本は、ぜひひとりでも多くの人に読んでもらいたいと思っています。著者のジェームス・ブライドルさんは、今、東京初台にあるICC(INTERCOMMUNICATION CENTER)で開催されている「オープン・スペース 2018 イン・トランジション」という展覧会(2019年3月10日まで開催中)で、自動運転車をテーマにした映像作品を展示しています。テクノロジーが不可知なものになることこそが「ダーク・エイジ(暗黒時代)」をもたらす。それはエンライトメント(啓蒙)の逆です。何ごとに対しても、妄信的に信じることなく、自覚的に考え続けることこそが、いつの時代にもとても大切ことなのです。
※NTT出版から11月30日に刊行予定。
http://www.nttpub.co.jp/search/books/detail/100002458.html

どんなにデータが増えても、どんなに処理速度が向上したとしても、世界は量子力学的に不確定で非自明なものであることには変わりません。天気予報と天気決定が違うように、未来予測と未来決定は根本的に違います。何を予測したとしても、それは考えることによって変えるべき対象であることを言わないといけません。ある特定のアルゴリズムが過去のデータから導いたものを、あたかも運命や宿命のように示したとすれば、それはもはや人をコントロールするための道具でしかないでしょう。
◆プロフィール

久保田晃弘
アーティスト
研究者
多摩美術大学情報デザイン学科情報芸術コース教授
1960年生まれ。東京大学大学院工学系研究科船舶工学専攻博士課程修了・工学博士。非線形数値流体力学、人工物工学(設計科学)に関する研究を経て、1998年から現職。衛星芸術プロジェクト(ARTSAT.JP)をはじめ、バイオアート、芸術活動の圏論による描写、ライヴ・コーディングによるサウンド・パフォーマンスなど、さまざまな領域を横断・結合するハイブリッドな創作の世界を開拓中。芸術衛星1号機の「ARTSAT1:INVADER」でアルス・エレクトロニカ2015ハイブリッド・アート部門優秀賞をチーム受賞。「ARTSATプロジェクト」の成果に対し、第66回芸術選奨の文部科学大臣賞(メディア芸術部門)を受賞。近著に『遙かなる他者のためのデザイン』(BNN新社・2017)『メディアアート原論』(共編著・フィルムアート社・2018)『インスタグラムと現代視覚文化論』(BNN新社・共編著・2018)『ニュー・ダーク・エイジ』(NTT出版・監訳・2018)などがある。

篠田 裕之
博報堂DYメディアパートナーズ
データドリブンメディアマーケティングセンター
データビジネス開発局 ビジネス開発部
兼 グローバルビジネス局 戦略企画グループ
データサイエンティスト。自動車、通信、教育、など様々な業界のビッグデータを活用したマーケティングを手掛ける一方、観光、スポーツに関するデータビジュアライズを行う。近年は人間の味の好みに基づいたソリューション開発や、脳波を活用したマーケティングのリサーチに携わる。
★本記事は博報堂DYグループの「“生活者データ・ドリブン”マーケティング通信」より転載しました

【関連情報】
■ データ・クリエイティブ対談 キックオフ座談会(前編)
■ データ・クリエイティブ対談 キックオフ座談会(後編)
■ データ・クリエイティブ対談 第1弾 ゲスト:ロボットクリエイター高橋智隆さん
■ データ・クリエイティブ対談 第2弾 ゲスト:長谷川愛さん(バイオアーティスト)
■ データ・クリエイティブ対談 第3弾(前編) ゲスト:久保田晃弘先生































