コラム
メディア・コンテンツビジネス
「“変わりゆくメディアと生活者〜媒体社×博報堂DYメディアパートナーズ、 データマーケティングによるアプローチとは〜”」 Vol.1デジタル化による出版社との関わりの変化とは
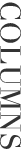

デジタル化が進むにつれて、媒体社の役割も大きく変化しています。本連載では、媒体社の変化と、それに伴い博報堂DYメディアパートナーズ(MP)の役割がどう変わってきたのか、今後どう変わっていくべきかをデータマーケティング視点で模索していきます。第1回の今回は、雑誌局の考える出版社との関わりの変化と今後について、雑誌局の瀧川千智に、データビジネス開発局の馬島久直が聞きました。
馬島:
データビジネス開発局の馬島です。生活者DMPをはじめとする各種データを活用して、メディアソリューションやマーケティングソリューションの開発を行っています。今日のテーマに近いところで言うと、媒体社の持っているデータと博報堂DYグループの持っているデータを掛け合わせて、媒体社の課題を解決するといった具合です。
以前は博報堂のマーケティングの部署にいて、今も複属しています。ソリューションを開発する際にはクライアントのマーケティング課題やコミュニケーション課題を解決するという視点が必要なので、マーケティングを担当した経験は現在の仕事に役立っています。
瀧川:
雑誌局の瀧川です。私も博報堂のマーケティングの部署に配属となり、洗顔料などのトイレタリーや通信分野などを担当していました。そこから雑誌局に異動し、マーケティングで培った調査などの経験を雑誌局で活かしたいと思って新しいビジネスの開発や、様々なことに取り組んでいます。
馬島:
今回は、前提として「媒体社のデジタル化が進んでいく中で、博報堂DYメディアパートナーズとして媒体社との向き合い方がどう変わるか」という視点でお話を伺えればと思っています。現状の雑誌局の取り組みを教えて下さい。
瀧川:
雑誌局というと紙媒体の誌面広告セールスのみと思われがちですが、今、「紙に縛られずに雑誌のコンテンツをどう活用していくか」を考えています。誌面での展開も勿論ありますが、デジタル上での展開が増えていて、誌面の広告枠を売るというよりはコンテンツをどう活用していくか、という流れになっています。
元々雑誌局は“出版社プロパティ”と呼んでいる出版社のリソースを、いろいろなタッチポイントと掛け合わせて展開するということをやってきました。たとえば、タイアップでつくったコンテンツを店頭POPに使ったり、抜き刷りでミニブックにしたり、電車のビジョンに使ったり、折込チラシにしたり、出版社のイベントを活用したり。その中でも最近はデジタルと掛け合わせる動きが多いです。
デジタルメディア展開の際も、WEBタイアップ記事を作るだけではなくて、動画を作ったり、媒体社のサイトに人を呼び込むため、ソーシャルメディアなどからの外部誘導もしています。博報堂DYグループのデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(DAC)が開発・提供するDMP「Audience One®」を活用して、媒体社のサイトを閲覧している人と似た特性の人を誘致したり、インフルエンサーを起用したり、といったこともWEBタイアップ広告とセットで実施しています。
馬島:
私はマーケティング部署の前は営業で、雑誌広告のセールスも担当していました。
当時は、雑誌で編集タイアップ広告を実施したら自社のWEBサイトに転載する流れはありましたが、最近はコンテンツを作ったらSNSに出したり、イベントに使ったりと、誌面のみに捉われない流れになっていると感じます。
瀧川:
以前は「誌面でタイアップ広告を実施してからWEBに掲載」という流れでしたが、最近は「WEBのみで掲載したい」というケースも増えてきました。デジタルでの展開は動画をつくり、WEBタイアップ記事に載せて、そのコンテンツを拡散していく、といった内容であれば効率的ですし。
馬島:
軸足がWEBに移って来てもいますが、コンテンツや編集のクリエイティブ力が依然として大事ですよね。誌面でよくある「この雑誌のこのテイストを出して欲しい」といったクライアントからの依頼は、WEB上での制作においても多いと感じます。媒体社の強みを実感する時はありますか。
瀧川:
出版社の場合、各雑誌に世界観があり、そのファンがいます。博報堂ケトルの嶋浩一郎さんが言っていたのが「雑誌にはレリバンシーがある」ということ。例えばカルチャー雑誌が車の特集をする場合、読者の方が「車には興味はないけどこの雑誌が言うなら考えようかな」ということが起きるんですね。欲望が全くない、ゼロのところから欲望を作ることが出来るのが雑誌です。それはまとめサイトなどにはない部分だと思いますね。
雑誌とのコラボレーションで様々な層にアプローチが可能になる
馬島:
企業が直接メッセージを発信するのではなく、雑誌の編集の方がメッセージを解釈してその雑誌ならではの切り口で発信すると、伝わる層や伝わり方が大きく変わりますよね。例えば、「経済誌の視点で企業を切る」といった視点から入って最終的にコミュニケーションしたい商品ブランドに落とし込んでいくと、企業がその商品ブランドを直接的に伝える場合とは文脈が違ってくるので、その企業への関心度がそこまで高くない層にも効果的にアプローチ出来ますよね。ストーリーとセットになるから強いですよね。
瀧川:
企業のファンやユーザー近くで固めるより、いろいろな業界を知っている経済誌の視点だと、違う層にアプローチ出来ますよね。
ある女性向けのライフスタイル誌が住宅メーカーとコラボしたのはいい例だと思います。家、というところから発想すると家を買いそうな人のみを対象としてしまうので、住宅展示場だったり、コラボするとしても住宅専門誌となりがちです。でも女性向けライフタイル誌であれば、「キッチンで料理がもっと楽しめる」など家そのものよりも生活を楽しむ方向を訴求出来るので、ターゲットを広げることが出来ます。
出版社の強みは、マーケティング的な部分で読者を知っているということと、クリエイティブ力です。ある主婦向け雑誌が、それまでは料理の話などをメインで取り上げていたのですが、読者の自宅訪問調査を行って読者の声を聞いた結果、主婦誌なのに「料理が苦痛である」ことをテーマにしたり、時短のやり方などを紹介する方向に転換して大きな反響を得た事例がありました。やっぱり読者がどういう人で、どういうコンテンツに興味があるかを分かっているんですよね。

馬島:
編集部が読者を理解していて、それがコンテンツ制作の核になっているということですよね。
出版社はデータ分析にはどれくらい取り組んでいるんでしょうか。
瀧川:
出版社によりますが、独自に取り組んでいるところは少ないかなという印象ですね。外資系の出版社だとWEBを担当する人材を雇ったり、データ分析システムがあったりしますが。まだまだ出版社の一部がデータ活用を始めたところ、というのが現状だと思います。
馬島:
私は分析やソリューションの開発でデータを活用するのですが、全てをデータで完結させようとすることには限界があるなと感じます。誰でも分かる、当たり前のことを示すような薄いものになってしまう。だから編集部の方の理解が深い領域をデータで証明したり可視化したりするといったやり方はメリットが少ないと思っていて、編集部の方の知見ではカバーできない部分をデータで補強するのが良いのではないかと思っています。例えば雑誌で今後のトレンドを発信していこうといった際に、イノベーターと考えられるような人たちがどんなものに関心を持っているのか、次に来そうなトレンドは何かといったことをWEB上の行動やその他アクチュアルデータから推測する、といった具合ですかね。
雑誌広告の効果検証のために作ったMAGA-CHECKとは
馬島:
データ活用の話になったので、瀧川さんが取り組んでいる「MAGA-CHECK」について教えていただけますか。
瀧川:
雑誌のWEBタイアップ記事において、ちゃんとした効果検証が出来ないことが長年の課題になっていました。そこで、出版社のデータを活用することで、WEBタイアップ記事の効果検証を出来るように開発したメニューがMAGA-CHECK(マガチェック)です。
MAGA-CHECKはAudienceOne ®と、それに連動したアンケート調査「「Querida調査」の二つから成り立っています。AudienceOne ®では読者の性別や年齢、趣味嗜好といった属性を把握し、Querida調査ではアンケートによって「こんなブランドを購入した」「どんな生活意識を持っている」「タイアップの印象はどうだったか」「ブランドに対する理解が深まったか」といったことが分かります。Querida調査は他の媒体に拡張配信する際のプラットフォームとしても使えます。
先日は、某雑誌のWEBサイトで、化粧品会社のタイアップの効果検証をMAGA-CHECKとして試験的にやらせていただきました。
その雑誌サイトの読者は、一般層と比べてコスメ意識が高いだけでなく、ファッション意識やライフスタイル全般で意識が高く、雑誌だけでなくSNSの利用も高いことが数字的に把握できました。
これまでの雑誌の「媒体資料」は、編集部が読者特徴をイメージで説明しているものが多かったのですが、MAGA-CHECKではそういった抽象的な特徴ではなく、具体的な数字で媒体を捉えられるようになった点は大きいと思っています。
MAGA-CHECKの出版社へのメリットは他にもあって、今回でいうと、出版社側が様々なコスメブランドに対するイメージやファネルのスコアをデータベースとして持てたことです。今後はこのデータを利用することでより効果的なクライアントセールスが可能になると思います。また効果検証が可能になることで、単発出稿ではなく継続出稿をしてPDCAを回しながらやっていきましょう、といった提案もしやすくなると思います。
馬島:
効果検証のフレームが出来ること自体に価値があると思います。どのコンテンツ、どの表現が効果的だったということが分かれば中長期的な運用が出来ますね。他の媒体にも展開出来るはずですし、クライアントの目線から言えば、どの雑誌ではどういった表現がいいのかということが分かるようになりますよね。
瀧川:
そうですね、クライアントからも出版社を比較することが出来るようになります。出版社からしたら比較されるのは若干嫌な部分もあるかと思うんです。でも、MAGA-CHECKはクリックなどの量的な部分ではなく、質的な部分を把握しようというものなので、「媒体ごとにどんなコンテンツ、内容が向いていて、どんな効果が期待できる」というのがはっきりと分かります。その結果として、より出稿が増えるのではないかと思うのです。今後はいろいろな媒体社に協力をお願いしたいと考えています。
馬島:
雑誌が興味や理解といったミドルファネルに効果があるのは感覚的にも理解が出来ます。最終的に購買までどう繋がったかまで見せられるようになればより説得力が高くなりますね。
瀧川:
コスト・パー・エンゲージメント(CPE)のような指標を作れたらいいなと思っているんです。消費者が購入に至るまでの意識の変遷をマーケティング用語で“ファネル”と呼びますが、“認知”などアッパーなファネルに効くのはテレビ等のマスメディアかと思いますが、“興味”や“理解”といったミドルファネルでの雑誌の効果は大きいと思っています。今回のテストケースでも、雑誌のタイアップが“興味”や“理解”に効くという傾向がみえました。ミドルファネルの数字が上がって、その結果CPEが上がったと言えれば、より効果を実感していただきやすいと思っています。
馬島:
デジタル領域では、やはりコンバージョンの数や効率は重要です。デジタル周りで取れるデータも増えているので、MAGA-CHECKで捉えた質的な変化が、アクセスした人にどういった影響を与えたかまで見えるようにできれば、より有用なのではないかと思います。
例えばテレビだとリーチする人数は獲得されやすいが、雑誌は人数だけで見ると苦しいかもしれない。でもどれだけ内容の濃い接触が出来たかを見ることが出来れば、雑誌の価値も上がるはずです。この考え方は昔からあるものだと思いますが。

瀧川:
雑誌の価値の広げ方でいうと、広告的な部分以外でも何らか活動できないかと考えています。例えば出版社の編集部は記事を作る以外にも、インサイト発見や、キーワード開発、商品のアイデアを出すなど、マーケティング力やクリエイティブ力を生かす方向が様々にあると思うんです。そこを価値にしてマネタイズできたらと。我々は編集部とクラインアントの間に入り、編集部だけではやりきれない部分のサポートをする。たとえばクライアント課題解決の視点のインプットだったり、総合的なプランニングや、調査やデータで証明していくといった動きも出来たらと考えています。
馬島:
媒体社は自社の強みを当たり前のことと思われていることが多いように感じます。でもクライアントから見るとすごく価値のあるものだと思いますし、だからこそ、そこを拡げられる可能性はまだまだあると思うので、今後の展開が楽しみですね。
本日はありがとうございました。
■プロフィール

瀧川千智
博報堂DYメディアパートナーズ
雑誌局 業務推進部
2005年博報堂入社。マーケティング職として8年従事し、化粧品、トイレタリー、飲料、通信会社などを担当したのち、博報堂DYメディアパートナーズの雑誌局へ。ファッション・コスメ・クルマなどを担当し、メディアプランニングやメニュー開発を行う。女性プロジェクト「博報堂キャリジョ研」のメンバーでもある。

馬島久直
博報堂DYメディアパートナーズ
データビジネス開発局 データビジネスデザイン部
2006年博報堂入社。営業にてマス・WEBのメディアプラニングの仕事に従事。2010年からマーケティングプラナーとして通信、金融、自動車等のクライアントでマーケティング戦略のプランニングや、デジタル領域の戦略・施策プランニング、PDCA運用の経験を積む。2015年に博報堂DYメディアパートナーズに異動し、データマーケティング領域の業務を担当。DMPを活用したマーケティング高度化やクライアント課題解決のためのソリューション開発を行う。































