レポート
セミナー・フォーラム
博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所ウェビナー MEDIA NEW NORMAL メディアの新常態を考える パネルディスカッション Report
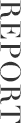
新型コロナウィルスの影響によって私たちの生活・ビジネス・社会は大きな変化を余儀なくされ、ニューノーマルと言われる「新しい生活様式、新常態」がもたらされました。メディア環境研究所は、生活者調査・取材・議論、オンラインイベントやレポートを通じて「メディアの新常態」について考察。その最新データをもとに今後のビジネスの視座を探るウェビナーを開催しました。本稿では第二部のパネルディスカッションの内容をご紹介します。
パネルディスカッション「変化の兆しは吉か凶か?」
パネリスト:
阿蘇 博(株式会社TBSテレビ 営業局関西支社 営業部長)
玉置泰紀(株式会社KADOKAWA 2021年室エグゼクティブプロデューサー)
モデレーター:
森永真弓(メディア環境研究所 上席研究員)

■コロナによって、メディア自身が大きく変わるチャンスがもたらされた
森永
モデレーターの森永です。阿蘇さん、玉置さん、今日はよろしくお願いします。一つ目の議題は「当たり前と普通を考え直す」ですが、先日の雑談で阿蘇さんに「コロナ前に戻りたい環境や雰囲気などは社内にありますか」と聞いたところ、「様変わりしすぎて戻れない感じ」とおっしゃっていたのが印象的でした。

阿蘇
たとえばバラエティ番組のセットは人と人の間隔を空けていますし、情報番組はコメンテーターにリモートで出演いただくことなどがベースになってきていて、意外と何とかなるなと感じています。ドラマの場合は、人の間隔を空けて制作するのはやはり難しいものがあるのは事実ですが。また、お店の取材などは、大勢のクルーを連れていくと断られるようなところでも、リモートや小規模の取材なら許可をいただけたりする。実は予算的にもそちらの方が良いというようなムードも見え隠れしてきて、変化を感じていますね。
森永
そうなんですね。玉置さんは以前雑誌「東京ウォーカー」について、「おでかけ情報をつくるという目的で組み立てているので、雑誌という形にこだわっているわけではない」というお話をされていましたが、その辺り詳しく聞かせていただけますか。
玉置
我々はまさにコロナの直撃を受け、「東京ウォーカー」「横浜ウォーカー」「九州ウォーカー」は6月20日を最終号に休刊、「関西ウォーカー」「東海ウォーカー」は紙も残っていますが、基本はウェブサイトの「ウォーカープラス」に移行しています。僕は新聞社、出版社を経た後、KADOKAWAで30年ほど「ウォーカー」をやってきましたが、実はそれほど紙媒体に執着はないんですね。キーノートでメディアの変遷について触れられていましたが、僕自身おでかけ情報を発信するに当たり、紙、ウェブサイト、モバイル、あるいはUstreamなども活用してきました。情報を流通すること自体に興味がありますから、むしろ紙にこだわらず複合的にやった方が面白いとずっと考えていました。
森永
なるほど。テレビの場合、今回のコロナの事態を受けて昔のドラマなどが次々放送され、時代を超えて反響を呼んでいました。どんなデバイスで見てもいいというような時代においても、アーカイブを活かすことができるテレビの強さのようなものを改めて感じたのですが、阿蘇さんはどうお考えですか。
阿蘇
たとえば「JIN-仁-」「逃げるは恥だが役に立つ」などは視聴率も良く反響もあって、やはりいい物を出せば視聴者はテレビを見てくれるということがわかりました。デジタルによって視聴手段が増えることで、SNSで拡散されまたテレビに戻ってくるという現象もあった。そういう意味で制作側も、いいものをつくれば何年たっても人は帰ってきてくれると思った部分はあると思います。
森永
それこそビジネス面では、テレビの放送や本の出版などのタイミングに限らず、マネタイズのタイムスパンをより長く広く考えられるようになったわけですよね。そういう風に見直すタイミングが来たという感じでしょうか。
阿蘇
そうですね。昔のアーカイブをどうやってもう一度世間や海外に広めていくかという点においては、社内でもコロナ以前から課題ではあったのですが、取り組むタイミングがちょうど来たという感じです。もともとテレビ局のビジネスモデル的に、営業はスポンサーと向き合うことが多く、制作は視聴者に向き合うことが多かったわけですが、つい7月にも社内にDX(デジタルトランスフォーメーション)局という局が新設され、制作や権利処理、営業などを一括してやるようなシステムも可能になりました。そういう意味でより生活者に近づいた仕事が増えるのではないかと感じています。
森永
DXというと、どうしてもテクノロジー面の話に注目してしまいがちですが、時代に応じて自分たちの本業の足元をもう一度見直し、棚卸しするという意味も大きいのかもしれませんね。玉置さんは以前、「コンテンツの一つ一つは確かでも、フォーマット上の演出をし始めた途端におかしくなってしまって、今はむしろ生っぽいものの方が求められているんじゃないか」と話されていました。“フォーマットの見直し”について教えていただけますか。
玉置
阿蘇さんの前でこんなことを言うのは口幅ったいのですが、緊急事態宣言を受けて長時間家にいた結果、多くの人がコロナの情報を知りたいと思ってテレビをつけ、延々と続くニュース番組やワイドショー番組を見ることになりましたよね。その結果、たとえば行政を批判したり、逆に批判するのはどうかといった議論になったり、従来のワイドショーの在り方というのを目の当たりにし、「イノベーションしてないな」と感じざるを得なかったのではないでしょうか。これは僕らの雑誌のつくり方においても言えることなのですが。
森永
少しだけ情報を出して脅してみたり、ちょっと泣きの話を入れたり…そうした演出パターンを踏襲しすぎということですよね。
玉置
僕もずっとメディア業界にいますが、メディアのフォーマットは意外に変わっていない。今回のコロナ禍を受け、多くの人が「元の世界に戻れない」と感じているのだとしたら、それはメディアにとっても変わるチャンスではないかと思います。キーノートでお話のあった、演出されたものよりも事実の提示が求められるとか、情報を得るだけではなく実用を求める動き…そういったものに、メディアも合わせていく必要があり、今はそれを考えるいい機会なのではないかと思います。
■テクノロジーが可能にする新たなメディア体験と、コンテンツの価値の見直し
森永
実際に今大きく見直されているものとして、音楽ライブやスポーツの観客の入れ方があると思います。キーノートにもあった「側にいる距離感」をつくるために、野球だったら球場の音の出し方や、放送の工夫もしている。ここで次のテーマ、「テクノロジーをどう使っていくか」について考えていきたいと思います。玉置さんが以前おっしゃっていた「eスポーツ用につくった箱」について詳しく教えていただけますか。

玉置
弊社は東所沢にサクラタウンという施設を作ったのですが、そこにeスポーツができるジャパンパビリオンというホールがあります。通信設備や放送設備が完備してあって、eスポーツの大会も企画しようとしていたのですが、あいにくコロナで中断してしまいました。ただ、もしそこで大会を開催するならば、ある程度観客席を入れて臨場感を出しながら、あとは完全にネット中継で見てもらうといった方向性が見えてきた。また、子会社であるドワンゴは「ニコニコ超会議」を主催していますが、去年は幕張メッセで2日間開催し、リアルで15万人、ネットで666万人が集まりました。10周年を迎えた今年はオンラインで「ニコニコネット超会議」を実施。8日間に期間を伸ばしてはいますが、実に1600万人以上の人がやって来たんです。さらに「超会議」よりも規模の大きなコミケは、今年東京ビッグサイトでの開催ができなかったため、エアコミケを行ったところ、そのインプレッションが3300万にのぼったそうです。リアルとデジタルの組み合わせ、あるいはデジタルの可能性に関して、このコロナの間は相当色々な問いかけがあったんじゃないかと思いますね。
森永
確かにeスポーツではリアルタイムに反応が返ってくることが重要で、アップロード回線とダウンロード回線の両方が太くなければならないということもありますよね。それ以外でも、たとえば今後スポーツの放送にもリアルタイム性が求められるようになって、家から歓声を届けたいというふうになった場合、スタジアム側の音響設備や回線設備などがいかに整備されているかが重要になってくるのかもしれません。
テレビの現場では、コロナ禍を受けて、何かテクノロジーを使った新たなコンテンツ制作の方向性などは出てきていますでしょうか。
阿蘇
最近の例で言うと、「人生最高レストラン」という番組のスタジオ収録がコロナの影響でできなかったため、総集編を流しながら、リモートで4名の出演者の部屋をつなぎ飲みながら語ってもらうという形にしました。豪華なセットではない分出演者の日常感が出ていて、Twitterの反応などを見ていても、共感のようなものは得られたという実感があります。スポンサーへの親近感も湧いたというコメントもありました。アナログに近いテクノロジーではありますが、今まで気づかなかったような新しいつくり方が出てきたという感じはしています。
森永
テクノロジーによって、実はその番組やコンテンツが一番届けたかったものを見直すような機会にもなっていると。
阿蘇
そうですね。コロナの常態化がこれからどう定義されるかにもよりますが、もしかしたら先ほど玉置さんが言っていたような、フォーマットをどう変えるかとか、場合によってはタイムテーブルをどう変えるかといったことも、メディアが向き合わなくてはならない課題だと思います。
■ますます求められる“生活者目線”の情報発信
森永
キーノートの最後にもあった、「レイトマジョリティ」についてはいかがでしょうか。これまで女性はマスメディアが割と得意にしていたターゲットだと思うのですが、彼女たちが変わっていくことでどんなことが起こりそうか、あるいは、それを受けてやってみたいことなどはありますか。

玉置
「東京ウォーカー」誕生後、地方でも様々なウォーカーをつくりましたが、読者の男女比は50:50なんですよ。でも女性に限って言えば、関西で「関西ウォーカー」が全盛だったころに行った調査によると、女性誌よりもウォーカーを見ている人の方が多かった。先ほど「情報より実用を求める動き」の話がありましたが、ウォーカーは実用的じゃなければ意味のない雑誌で、それを見てどこかに行けたり、買えたりと、何かに使えないと本当に買ってもらえない。そして男性が面白さを求める一方で、実用を求める層の大半が女性なんです。
森永
テレビに関してはいかがでしょうか。これまで受け身だった視聴者が能動的になるというようなことを、どう捉えてらっしゃいますか。
阿蘇
そうですね。ここ最近、やはり僕らもSNSの反応を非常に参考にするようになりましたし、これまでテレビが気づいていなかった事実――視聴者が離れていることに、ようやく気付くようになってきたのではないかなと個人的には思います。そういう意味で言うと、生活者に向けた、あるいは生活者の意見が反映されたコンテンツ、商品づくりというものに、今後は向き合っていかなくてはならないとも考えています。
森永
ありがとうございます。
ここで、チャットでいただいた質問を見てみましょう。阿蘇さん、「再放送ドラマの売り上げはどうですか?ヒットコンテンツと言えど、一般的な新ドラマの提供より安いのでしょうか。あるいはスポンサーは、再放送も新ドラマと同等の価値を感じているのでしょうか」という質問が来ています。
阿蘇
正直非常に答えにくい質問ですね(笑)。スポンサーからはもちろん同程度の価値は望まれていますし、再放送だから値段が安くなるといったことでもありません。結果として視聴率も含めて視聴者の賛同が得られることが価値になる、というビジネスになっています。
森永
ありがとうございます。では次に「メディアが視聴者や消費者の心理的な距離を詰めるために必要なことは?」という質問が来ています。
玉置
僕がウォーカーでやってきたことは、読者目線、使う人目線になること。編集者目線で作るなということを、新人にもいつも言ってきました。編集者というのはどうしても上から俯瞰してものを考えてしまうのですが、実際に動いている人の目線で考え、作らなければ、ウォーカーを使ってもらうことができない。編集するというのは僕らの唯一のスキルなので、見栄えや仕上がりを意識してしまいがちですが、そればかりを意識してしまうと使う人の視点とずれが生じてしまう。少なくとも、実用性のない仕掛けは外さなきゃいけないなと思います。これまでの編集の考え方、価値というものも見直す時期になっているのかもしれません。
森永
阿蘇さんはいかがでしょうか。
阿蘇
これはラジオの話ですが、TBSラジオの番組制作や編成の会議でも、デジタルとの融合が強調されるようになってきました。キーノートでも出てきましたが、ラジオと雑誌のメディア接触時間が伸びているという現状は、ひとえにデジタルとの連動があってのことだと思います。今後はテレビやSNSとの連動も出てくるかもしれませんし、リスナーに近いラジオだからこそ、そういう目線もコンテンツ作りにフィードバックしていけたらいいのかなと思います。
森永
この3、4年くらいはTwitterのトレンドにラジオ番組があがってくるのが当たり前のようになってきました。若者の方がフォーマットやデバイスにこだわらず、フラットに面白いものを探しているというのは、私自身も感じるところです。
では最後に、変化が続く中ですが、今後半年、1年とどのように過ごしていかれる予定かをお聞かせください。

玉置
来年のオリンピック、パラリンピック、そして2025年の万博にからめて、これまでのメディアに収まらないようなことをKADOKAWAのIPでやろうとしています。統合型リゾートのIRもあります。これらは今逆風の中で全然進んではいませんが、一所懸命取り組んでいるところです。先のことは不安ではありますが、こういうときだからこそ何をすべきかを日々考えているところですね。
阿蘇
僕の場合は営業目線になってしまいますが、一般の人が求めている情報の鮮度や、複数のメディアを活用するような志向に、今後いかに目を向けていくかが大事だと思っています。そしてそれを支えるメディア連携をどう編み上げていくか。営業と制作経験者が一緒になって、スポンサーの要望にどう応えるか、その先にいる視聴者の声をどう集め、番組づくりに反映させるかといったことに、向き合っていければと考えております。
森永
お2人ともありがとうございました。

阿蘇 博
TBSテレビ 営業局 関西支社 営業部長
94年TBS入社。入社以来20年にわたりセールス・デスク業務に携わる。営業以外で『K-1world max』『SASUKE』等のスポーツ、アニメ『学園BASARA』『ザックリTV』等の企画制作の他『熊川哲也kバレエ』のプロデュースに携わる。2020年7月から2度目の関西支社赴任。

玉置泰紀
KADOKAWA2021年室 エグゼクティブプロデューサー
産経新聞社会部記者を経て、福武書店月刊女性誌、角川で編集長4誌、元ウォーカー総編集長を歴任。大阪府日本万国博覧会記念公園運営審議会会長代行。日本IRビジネスリポート編集委員。京都市埋蔵文化財研究所理事、東京文化資源会議幹事。

森永真弓
メディア環境研究所 上席研究員
通信会社を経て博報堂に入社し現在に至る。 コンテンツやコミュニケーションの名脇役としてのデジタル活用を構想構築する裏方請負人。 テクノロジー、ネットヘビーユーザー、オタク文化研究などをテーマにしたメディア出演や執筆活動も行っている。自称「なけなしの精神力でコミュ障を打開する引きこもらない方のオタク」。 WOMマーケティング協議会理事。共著に「グルメサイトで★★★(ホシ3つ)の店は、本当に美味しいのか」(マガジンハウス)がある。
【関連情報】
★博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所ウェビナー MEDIA NEW NORMAL メディアの新常態を考える キーノート Report































