レポート
アドテック東京
【アドテック東京2018レポート】企業がイノベーションを起こすには、外部の視点が必要だ
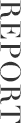

左から、博報堂DYメディアパートナーズ 常務執行役員 三神正樹、Wes Nichols氏、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc. 個人事業部門デジタルマーケティング副社長 友松重之氏
2018年10月4日、5日の2日間にわたって開催されたマーケティングとテクロノジーに関するカンファレンス「ad:tech tokyo 2018」。1日目に「テクノロジーが全てを変えていく時代に我々はどう備えるか」というタイトルでセッションが行われました。シェアリングエコノミーやAIを使ったサービスなど、新しいビジネスが続々とスタートしている現在の状況に、長年ビジネスを展開してきた日本企業はどのように対応すべきなのでしょうか。
博報堂DYメディアパートナーズ 常務執行役員 三神正樹とアメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc. 個人事業部門デジタルマーケティング副社長 友松重之氏がスピーカーを、Upfront VenturesのパートナーであるWes Nichols氏がモデレーターを務めました。
Wes:Wes Nicholsです。UberやAirbnb、Google/Facebookなど、テクノロジーを使って新しいビジネスをスタートした企業が、旧来のビジネスのルールを変革しています。こういったイノベーションが起きている状況において、企業はどのように備えるか、今日は皆さんとお話したいと思います。
三神:博報堂DYメディアパートナーズの三神です。Wesとは彼が創業したMarketShareという会社とは共同のプロジェクトに取り組んだ経験があるので、長い付き合いになります。その時のMarketShareの日本の責任者が友松さんでした。友松さんとも今日久しぶりに再会しました。
友松:アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.の友松です。いまご紹介いただいた通り前職はMarketShareでアジア代表を務めていました。私は電通Y&R、ジョンソン・エンド・ジョンソン、日本コカ・コーラ、GEなどでマーケティングやテクノロジーを担当しました。
Wes:では今日のテーマについてです。過去に大きな成功をした企業が、そのビジネスの内容を変えていくのがいかに難しいかをよく感じます。皆さんはどうですか。
三神:特に日本企業は困難に直面していると思います。一つの大きな理由は、過去50〜60年で日本企業が世界でも例をみないほどの成功を収めたことです。これがそのまま、変化することの難しさに繋がっていると思います。

友松:これまで多く転職した経験からすると、グローバルカンパニーには成功体験があり、「どうしてこれまで上手くまわってきたのに、変えなくてはいけないんだ」と考える人が多くいます。そういう会社がイノベーションを起こしたいと考える場合は、外部から人を雇い「社内の空気を読まず、一気に変えてほしい」と依頼するケースが多いですね。そうしないと競合がどんどん登場し、シェアを徐々に奪われてしまいますから。
Wes:文化について話しましょうか。三神さんはかなり長い期間をカリフォルニアで過ごされたのでお分かりかと思いますが、カリフォルニアには失敗してもいいんだ、という文化があります。中国にもそういうところがあり、新しいものをすぐに取り入れます。しかし日本は違うように感じます。
三神:日本の場合、組織と個人で話が違ってくるように思います。日本でも若者はスマートフォンなどの新しいモノやサービスをすぐに取り入れます。しかし企業となると、ディテールに完璧さを求める傾向が非常に強いため、ミスを恐れがちです。一方で中国企業はディテールにこだわらず、もっと大胆に取り組みますよね。
Wes:完璧さはイノベーションの敵になる、ということですね。システム開発で言えば、順々にしっかりつくっていくウォーターフォール型の開発と、素早く小さく完成させてその後改善を続けるアジャイル型の開発の違いですよね。
“ラストワンマイル”をAIが変える
Wes:スタートアップ企業の文化についてはどう思いますか。日本での資金調達の状況はどうなっているのでしょうか。

三神:ここ10年で日本のスタートアップを巡る環境は大きく変わったと思います。インディペンデントなベンチャーキャピタルだけでなく、コーポレートのベンチャーキャピタルもスタートアップに投資するようになりました。
友松:そういった環境がプラスに影響して、起業する人はどんどん増えているように感じますね。
Wes:テクノロジーによって、メーカーが生活者に直接商品を売ることができるようになってきていますよね。それもスタートアップにとっては大きなメリットだと思います。
友松:直販のブランドが増えていると聞きますね。ブランドと生活者の関係がこれまでにないくらい直接で、双方向で透明になってきている。販売だけでなく、プロモーションも直接できます。ダイレクトブランドは、間に流通や物流が入らない分、究極のデータドリブンマーケティングだと思います。
Wes:Googleの事例ですが、彼らのテクノロジーを使えば美容院やレストランへの予約の電話をAIが代わりにやってくれます。窓口がデジタル化していなくても、AIなどを使って予約できる時代が来ているということです。
三神:どんなビジネスも、「ラストワンマイル」が重要と言われていますね。eコマースがどんなに発展しても、物流の最後は人が届けなくてはいけません。スモールビジネスの場合、現在でも約60%がオンラインでは予約できないというデータがあります。Wesが例に上げたように、このラストワンマイルの部分をAI技術で自動化できる可能性はありますね。
Wes:医療診断の場合、80%の問題については医師よりもAIのほうが漏らさずに発見できるそうです。このようにメリットは膨大にあります。AIを広告会社やマーケッターが使うとどんなメリットがあるでしょうか。
三神:デジタルマーケティングに関する様々な機能を、企業が内製に切り替えている傾向があるのは事実です。大部分の企業がそうだとは感じませんが、デジタル上で顧客獲得を考える企業の場合は自然な流れでしょう。
友松:日本企業の場合、広告会社がかなりの部分までサポートしてくれているので、広告会社任せにし続けている企業も依然として多いと思います。インハウスも大事ですが実際に広告会社が果たしている役割も大きいので、企業は今後、どこまでをインハウスにして、どこをパートナーに任せるのか考えていく必要があるでしょう。

広告会社は“外部の視点”を提供する
Wes:企業はマーケティングのどういったところに関心を持つべきですか。
三神:広告会社の未来がどうなるかということよりも、日本の様々な企業がもう一度イノベーションを起こせるのか、その際に広告会社はそのパートナーとして寄与し得るのかということが大事だと思っています。新しいものを一緒につくり、古いものを一緒に壊すパートナーになれるのかが問われていると思っています。
Wes:広告会社が提供できるのは外部の視点ですよね。企業が自社の内部からイノベーションを起こすっていうのは滅多に起きない。地球上で最もイノベーティブな企業であるGoogleですら、イノベーションを起こすために買収をしているくらいですから。
三神:今はクリエイティブとテクノロジーが、マーケティングやビジネス全体に必須の時代です。クリエイティブとテクノロジーの高度なバランスが求められています。広告会社とのパートナーシップ以外にも、異業種の企業同士がジョイントするなど、外部の視点を意図的に増やす取り組みが増えているのも感じますね。
友松:全ての仕事を自社だけでやることは不可能ですからね。企業の場合、雇った人の限界がその企業の限界になります。限界を乗り越えるためには、外部の視点が欠かせません。
Wes:広告会社が提供する外部からの視点の価値は、今後も変わらないかもしれませんね。まだまだ話し足りませんが、本日はありがとうございました。

◆プロフィール

三神 正樹
株式会社 博報堂DYメディアパートナーズ
常務執行役員
1982年博報堂入社。IT部門、事業・プロモーション領域を経て、96年日本の広告会社初のインターネット専任組織「博報堂電脳体」設立に関与。以降、統合マーケティングやデータドリブンマーケティング等を実践、デジタル分野を牽引。2010年博報堂執行役員。11年博報堂DYメディアパートナーズi-メディア領域担当執行役員。 16年博報堂、博報堂DYメディアパートナーズ常務執行役員兼任。18年博報堂DYメディアパートナーズ常務執行役員、CISO兼イノベーションセンター担当(現職)。 「カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル」にて13年メディアライオン、16年イノベーション部門の審査員を務める。

友松 重之
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.
個人事業部門 デジタルマーケティング 副社長
電通Y&Rでキャリアをスタートし、その後J&J、日本コカ・コーラ、GEでブランドマーケティング職に従事。ヤフージャパンでのマーケティング本部長を経て、マーケティング投資分析コンサルティングで世界有数の米MarketShare社 アジア代表を務める。2016年5月 アメリカン・エキスプレスへ入社し現職に着任。デジタルでの新規カード会員獲得、テクノロジー開発の責任を持つ職責を担う。 米国でのマーケティングMBA。ブランドマーケティング、Webマーケティング、データ分析などにおける幅広い知識と経験、国内外の広範な人的ネットワークを有する。

Wes Nichols
Upfront Ventures
Board Partner
MarketShare創設者兼CEO。3つの公開企業と3社の民間企業のボードディレクターであり、米国最大のVC会社の1つであるUpfront Venturesのボードパートナー。
★こちらのコラムは博報堂DYグループの「“生活者データ・ドリブン”マーケティング通信」より転載しました
































