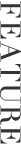「LINE Planning Contest」は、LINEが提供する各種法人向けサービスの販売・開発のパートナーを対象として、企画力を競うコンテストで、協賛企業のRFP(提案依頼書)に対して、優れたプランを提出したパートナーを「Planning Partner」として認定しています。特に優秀なプランは「最優秀賞」「優秀賞」として表彰されます。3回目となる「LINE Planning Contest 2021」で優秀賞に選ばれたのが、博報堂DYメディアパートナーズとデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(以下DAC)の混成チーム「REDぺっぱーず」です。全員が20代のプランナーという若手チームがこのコンテストで評価された理由とは何だったのでしょうか。5人のメンバーが、コンテストにかけた想いと受賞までの取り組みについて語りました。
池本 楓
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム
プラットフォームストラテジー本部ソーシャル局 LINE推進部リーダー
穴井 峻大
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム
プラットフォームストラテジー本部ソーシャル局 LINE推進部
伊藤 杏
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム
プラットフォームストラテジー本部ソーシャル局 LINE推進部
伊谷 祐太
博報堂DYメディアパートナーズ
プラットフォームビジネス局第三グループ
林 尚希
博報堂DYメディアパートナーズ
プラットフォームビジネス局第三グループ
<肩書は全て取材当時(2021年3月)のものです>
全員20代のチームで挑んだコンテスト
──「LINE Planning Contest 2021」とは、どのようなコンテストなのですか。
池本
LINEを活用してクライアントの課題を解決するプランニング案を競うコンテストです。私たちが参加した第3回目のコンテストは、3社のクライアントの課題から1つを選んで解決案を考えるというものでした。私たちが選んだのは、本田技研工業の「LINEを活用したファンマーケティング施策」でした。一次審査では5枚のパワーポイントに企画をまとめ、最終審査ではクライアントとLINEのご担当者にオンラインでプレゼンをしました。
──コンテストに参加しようと考えたきっかけをお聞かせください。
穴井
今までもコンテスト開催はあったのですが、私は参加をしていませんでした。LINEチームになって3年目の今年こそは主体的にコンテストに参加し、良い結果を残したいと考えていました。そこで、コンテストの案内が来てからすぐに、ともにLINEを担当しているDACと博報堂DYメディアパートナーズのメンバーに参加を呼びかけました。「REDぺっぱーず」というチーム名は、最年少の林くんが考えてくれたものです。

林
「RED」は、博報堂DYメディアパートナーズの本社がある赤坂と私の上司の名前からとりました。それに刺激的なアイデアを出そうという思いを込めて「ぺっぱー」とつけました。
──皆さん、誘われたときはどう思いましたか。
伊藤
私は入社2年目だったのですが、本格的なプレゼンの経験はそれまでほとんどありませんでした。経験を積むのに良い機会だったので、ぜひ参加したいと思いました。
伊谷
私と林くんは入社1年目で、新人研修でプランニングのロールプレイを体験していました。その実践ができるチャンスをいただけたと思いましたね。
林
かなりしっかりしたトレーニングをしていたので、参加への抵抗はまったくありませんでした。
池本
メンバー全員が20代なのですが、その中で最年長だった私が自然にリーダーという立場になりました。LINEを担当してからまだ1年に満たなかったのですが、デジタルメディアの業務推進や営業などを担当してきたので、その経験を活かせると考えました。
「本質」を考えることに時間をかける
──一次審査まではどのような流れだったのですか。
池本
コンテストの案内があったのが2020年10月初旬で、一次審査応募が12月、最終プレゼンが1月でした。時間があまりなかったので、最初からある程度の役割分担をしました。穴井くんと伊藤さんにはLINEで何ができるかを考えてもらい、伊藤さんには自動車業界の過去のキャンペーン情報のデスクトップサーチもしてもらいました。それから、新人だった伊谷くんと林くんには、新鮮な発想力を活かした企画づくりを主に担当してもらいました。
伊藤
仕込みに2カ月くらいかけましたよね。私たちは、いくつかある課題の中で本田技研工業を選択したのですが、同社の課題だけでなく、業界全体の課題について情報収集をしたり、断片的なアイデアを持ち寄ったりしながら、企画のベースをつくっていきました。
伊谷
情報収集して、分析して、みんなで考える──。その時間を長めに取ったことがいい結果につながったと思います。
池本
すぐに具体的な解決案を考えるのではなく、そもそもファンってなんだっけ、ファンコミュニティってなんだっけ、デジタルってどう使えるんだっけ、という本質的なところを考たことで、アイデアが深まりましたね。
林
難しかったのは、収集した情報やメンバー間の議論を企画にまとめ上げていくプロセスでした。
穴井
私たちの日常的な仕事は、営業担当から「こんな企画をクライアントに提案したい」というお題が与えられて、そこからアイデアを練っていくケースがほとんどなので、ゼロから企画をつくる経験はありませんでした。その意味では、メンバー全員にとって大きなチャレンジだったと思います。
──一次予選の時点で見えていた方向性はどのようなものだったのですか。
林
私たちが考えるファンの定義は、その時点である程度明確になっていました。ファンは「Honda」ブランドに対して積極的な好意をもっている人で、コアファンはブランドを何らかの形で「サブスクライブ」している人である、という定義です。サービスや製品を継続的に利用していたり、公式アカウントをSNSでフォローしたりして、ブランドと常につながっている。それがコアファンということです。

穴井
企画案は、ブランドの「スピリット」に対してファンになってもらうという軸と、「製品」に対してファンになってもらうという軸の2軸で構成しました。難しかったのは、それをパワーポイント5枚にまとめる作業でした。いかにシンプルに、わかりやすくまとめるかに知恵を絞りました。
伊谷
伝えたいことはたくさんありましたが、情報を入れすぎるとわかりにくくて見づらいスライドになってしまいます。まずは、一次審査を通過するための最低限の内容を伝えて、そこから最終審査につなげていくというのが私たちの戦略でした。
伊藤
最終審査ではスライドの枚数制限はないから、最終審査の企画にたくさん盛り込めばいい、一次審査の時点で「続きを見たい」と思ってもらえることが大切──。そんなことをみんなで話しましたよね。
池本
私は、企画案をまとめる過程で「絶対に一次審査は通過する」という自信はありました。でも、メンバーはみんな若くて経験値は決して高くはないので、思わぬところで減点される可能性もあります。だから、まずは「負けない試合」をすることが大事だと考えました。提案依頼書の内容を何度も何度も読み返して、求められていることに本当に応えられているかをしっかり考えて、減点の可能性をゼロにしたうえで、そこにプラスの要素を積み上げていく。そんな考え方です。
──一次は書類審査だったのですか。
穴井
そうです。スライド5枚のみでの審査だったので、審査をされる方の反応が見えない点は不安でしたね。
林
私は池本さんと同じように、一次審査は絶対通過すると確信していました。それくらい力のある企画だったと思います。
伊谷
私も少なくとも減点はまったくないだろうなと思っていました。
伊藤
「もし落ちたとしたら、その理由がわからない」というところまでやり切った。その実感は全員がもっていましたよね。
短い時間で走りながら成長できた
──そうして見事一次審査は通過したわけですね。そこから最終審査のプレゼンまではどのくらいの期間があったのですか。
穴井
実質2週間くらいだったので、時間との勝負でした。最終審査ではボリュームの規定がなかったぶん、どこまでストーリーを膨らませられるかも考えなければなりませんでした。
伊藤
結果的にパワーポイント50枚くらいで、ざっくり3パートに分ける構成になりました。最初のパートで重視したのは、本田技研工業の課題やスピリットに対して私たちがどれだけ真摯に考えてきたかを伝えることでした。提案の全体のテーマは「夢」で、本田技研工業が以前から掲げていた「The Power of Dreams」というメッセージに対する私たちの解釈を説明しました。
伊谷
まずは「熱量」を伝えるということですよね。私はそこのパートのスライドづくりを担当させてもらいました。また、熱量がストレートにクライアントに伝わるように今着ているパーカーもデザインして制作しました。
池本
ブランドの課題について必死に考える中で、私たち自身が「Honda」ブランドの熱烈なファンになっていました。まずは、その思いをしっかり伝えることが大切だと考えました。
穴井
提案した具体的なプランニングは、まだ「Honda」ブランドのファンではない人をファン化する2つの施策と、ファンをコアファン化するという合計3つの施策でした。一つ目は「シェアトラ」という企画で、LINEで自分の「夢」を宣言し、夢への挑戦の過程を多くの人とシェアするというものです。「トライ」を「シェア」するということですね。夢の達成率によって、「Honda」からのインセンティブが提供される仕組みを考えました。
伊谷
2つめが「Dream in Theater」です。最寄りのディーラーに足を運び、そこで車をレンタルしてドライブインシアターに行って、「The Power of Dreams」をテーマにした映画やブランドムービーを見てもらうという企画です。プロダクトを体験しながら、ブランドのメッセージを感じてもらうことを目指しました。
林
3つめの「Honda Universe」は、オリジナルコンテンツをつくり、LINEを含むさまざまなプラットフォームを横断してそのコンテンツを語り合うことでファンコミュニティを形成するという企画でした。
池本
プレゼンターは15分という時間の中で聞きやすさを考慮して3名に決めました。私と穴井くんと伊藤さんがプレゼンをして、伊谷くんと林くんには最初の30秒で雰囲気づくりをしてもらいました。そこまで本当に頑張ってきたので、プレゼンの話し方がうまくいっていなかったとしても本田技研工業やLINEにはきちんと伝わる内容が作れているはずだと思うようにしました。そのため、それほど緊張せずにプレゼンに臨むことができましたね。
穴井
制限時間は全体で15分です。1人の持ち時間は5分ずつでした。台本を用意して、本番前に上司の前で予行演習をしたのですが、「もっと気持ちを前面に出したほうがいい」と言われました。本番では、時間のコントロールをしっかりするだけでなく、気持ちを伝える話し方を心がけるようにしました。
伊藤
私はかなり緊張しましたが、結果的には自分でも満足できるプレゼンができたし、審査員の皆さんも途中で何度もうなずいてくださっていました。
伊谷
完璧なプレゼンでしたよ。
林
ほんと手応えがありましたよね。絶対大丈夫だと思いました。
池本
今から振り返ると、一次審査のときのレベルのままで最終審査に行ったら、おそらく受賞できていなかったと思うのです。最終審査に向けて、「本田技研工業にしか成し得ない施策」というところまで企画を深めることができました。短い時間の中で走りながら成長できたことが最終審査での成功につながったのだと思います。
ブランドが社会に求められていることは何か
──優秀賞に選ばれたと聞いたときの感想をお聞かせください。
穴井
率直にとても嬉しかったです。最終審査に残ったのは、本田技研工業含む3企業それぞれ5チームずつの計15チームでした。優秀賞に選ばれるのは、そこから各企業ごとに1チームだけですから、本当にすごいことだと思いました。
伊谷
みんな、受賞の瞬間は会議室で飛び跳ねて喜んでいましたよね。
伊藤
受賞を聞いた瞬間の記憶があまりないのですが、私が一番飛び跳ねていたようです(笑)。
池本
発表のときが、チームが一番まとまった瞬間だったかもしれませんね。
──どのような点が評価のポイントとなったのでしょうか。
池本
コロナ禍が続くこの状況の中で、本田技研工業が社会に求められていることは何か。それをしっかり考えたプレゼンだったと言っていただきました。あとは、施策の具体的な内容も評価していただけたようです。
伊谷
本田技研工業にやるべきことが何かが最初に伝わってきたと言っていただけましたよね。私たちが考えるクライアントの使命や、そのブランドだからこそできることをお伝えして、それを受け止めていただけたことが何よりも嬉しかったです。
伊藤
自分たちの熱量が伝わるプレゼンを私たちは目指したのですが、いただいた講評もすごく熱量のこもったものでした。そこにすごく感激しましたね。
穴井
自分たちの思いだけでなく、確実に実現できる施策を提案し、プロダクトを生活者に体験してもらうところまでの動線を描けたことも、評価をいただけたポイントだったと思います。
林
個人的には、新人研修で叩き込まれた生活者発想がこのプレゼンにいかされたと考えています。本当に生活者に面白いと思ってもらえる企画、自分も参加したくなるような企画であるといったコメントもいただきました。
LINE活用のあらゆる要望に応えていきたい
──この経験から得た学びとはどのようなものでしたか。
伊谷
アイデアは、その実現性まで考えて初めてアイデアとなるということを学ばせていただきました。それから、求められたことに100の答えを返すのではなく、120、150にして返すことが重要ということも、この取り組みの中で学んだことです。新人のうちにこのような経験ができたことは、本当に大きな糧になったと感じています。
伊藤
私にとって大きかったのは、チームメンバーからの学びでした。先輩の池本さんと穴井さんからはアイデアのまとめ方やプレゼンの仕方などを教えてもらい、後輩の林くんと伊谷くんからは発想の柔軟性を学ばせてもらいました。プランナーとしてステップアップできたという確かな実感があります。

林
企画づくりで成長できたことはもちろんですが、その企画がクライアントのもとまで届くのを見ることができたことも大きな経験でした。今後は、メディア担当の私たちから発信する企画にもぜひチャレンジしていきたいと思っています。
穴井
自分からみんなに声をかけて、それが成功体験に結びついたことが何より大きな自信になりました。それから、いい企画をつくるには、チームの中でぶつかり合うことも必要だということもわかりましたね。この経験をいかして、営業やクリエイティブの皆さんとぶつかり合いながら、優れた提案をしていけるようになりたいと思います。
池本
私は、リーダーという立場でチームに参加させてもらったことで、視野がとても広がりました。自分が営業だったら、クリエイティブだったら、クライアントだったら、プラットフォーマーだったら──。そんなさまざまな視点でものごとを考えることができるようになった気がします。
今回のコンテストで、博報堂DYメディアパートナーズは博報堂DYグループ初のLINEのPlanning Partner*に認定されました。この経験で得たものをグループのいろいろな人たちと共有して、グループ全体のプラニング力につなげていければいいですよね。
(※1)「Planning Partner」とは個人・法人向けアカウントサービス「LINE公式アカウント」を中心軸とした広告商品、およびAPI関連サービスの企画・運用を支援するパートナーです。Planning Partnerは年に1度開催されるプランニングコンテストで選出されます。LINEの仕組みを活かしたビジネスソリューションの提案ができているか、LINEの勉強会等へ積極的に参加する意欲とリソースがあるかなどを基準に認定されます。
──クライアントの課題解決力やニーズに応える力が格段に高まったと言えそうですね。
池本
おっしゃるとおりです。広告、販促、LINE公式アカウント活用と、LINE活用のあらゆるご要望に応えられるポテンシャルがこのチームにはあると思います。まだみんな若手ですが、プライドが仕事の邪魔をしたり、アイデアが偏ったりしたりしないのがこのチームの一番の強みです。LINEを活用してビジネスを成長させたい、そんな想いをお持ちの企業の皆さんは、ぜひ気軽にご相談いただければと思います!


池本 楓
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム
プラットフォームストラテジー本部ソーシャル局 LINE推進部リーダー

穴井 峻大
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム
プラットフォームストラテジー本部ソーシャル局 LINE推進部

伊藤 杏
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム
プラットフォームストラテジー本部ソーシャル局 LINE推進部

伊谷 祐太
博報堂DYメディアパートナーズ
プラットフォームビジネス局第三グループ

林 尚希
博報堂DYメディアパートナーズ
プラットフォームビジネス局第三グループ