コラム
メディア・コンテンツビジネス
人が集まる場所にはワケがある 「Media Hotspots」 第1回 映画『カメラを止めるな!』【前編】
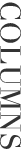

個人化、多様化、分散化が進み、個人すら捉えにくくなる現在。それでも、多くの人が集まる熱いメディア/コンテンツは存在します。その熱さを生み出した方々にメディア環境研究所所長 吉川がお話を伺うこのシリーズ。記念すべき第1回は映画『カメラを止めるな!』。その上映拡大にいち早く乗り出したアスミック・エース株式会社代表取締役会長の村山直樹さんに、ブーム誕生までのプロセスと今後のコンテンツ産業のキーポイントをインタビュー。「カメ止め」の熱さの秘密に迫ります。
偶然の出会い×スピード対応が生んだ「熱量の交換」
2018年、映画界に巻きおこった“事件”だった。インディーズ映画として制作され、6月23日に公開された『カメラを止めるな!』が、12月現在で観客動員222万人を突破し、興行収入は31億円を超えています。上映は都内2館での予定から、全国340館にまで規模を拡大し、未だにその勢いとファンの熱量は衰えません。
前編は、『カメラを止めるな!』を支えたアスミック・エース社員の「情熱」と、ファンの勢いを後押ししたソーシャルメディアへ考察を深めます。
 映画『カメラを止めるな!』公式サイトより
映画『カメラを止めるな!』公式サイトより
たった一人の「映画好き社員」の情熱から始まった
吉川 アスミック・エースさんが配給を決めるまでには、どんな流れがあったのでしょうか。
村山 もともとの経緯は6月23日に新宿(昼間3回上映)と池袋(レイトショー1回上映)のミニシアター2館だけで公開が始まった『カメ止め』ですが、たまたま噂で新宿が満員札止めらしいと聞きつけた弊社社員が7月1日に観に行って、あまりにも面白くてびっくりしたと。
吉川 偶然なんですか。
村山 そう、偶然。「これはすごい!」とテンションが上がり、すぐ交渉へ向かおうと言い出しました。「まずは社内でも作品をチェックしてみよう」と話が始まり、配給営業のメンバーが観ても「これはやりたい!」となったんです。TOHOシネマズに話を持ち込み、ご担当者にもすぐに池袋のレイトショーで観ていただき……バタバタと3週間後には全国公開が決まりました。

熱量が強い作品だからというのもあるけれども、関わるスタッフにも熱量があり、その熱量にスピードが加わった形ですね。7月25日には8月3日からの全国配給を発表し、TOHOシネマズ 日比谷の大きな劇場を空けて拡大公開御礼舞台挨拶まで持っていきました。とりあえず40館を開け、とんとん拍子で40館から180館、さらに200館と広がった。映画業界の普通のスピード感ではありませんね。
吉川 本来としては、もっと時間をかけることが多いのでしょうか?
村山 もっとゆっくりです。配給営業は通常、半年や1年先の営業を掛けますから。
吉川 僕も公開初期に足を運んだのですが、パンフレットなども売り切れ御免といった感じで、入荷予定も未定のままだったことを覚えています。
村山 実は、製作会社のENBUゼミナールさんが公開当初からパンフレットやTシャツの劇場グッズ展開を行っていましたが、拡大公開に伴って劇場数が増えていく中、ENBUゼミナールさんのマンパワーでは納品が対応できなくなりそうだったところを、アスミック・エースで劇場グッズと合わせて商品化展開についてもお手いをさせていただくことになったのですが、これも珍しいことです。

吉川 通常であれば、売れる見込みの少ないグッズを手がけたのは、なぜですか?
村山 Twitterですね。ツイートを見ると「演者が着ているTシャツはないのか」と。チラシがない、Tシャツがないなど、お客さんの反応がすごかった。全てのきっかけがTwitterの反応です。実際、グッズは劇場でもすぐ売り切れてしまうし、公開劇場が増えるごとにツイートも増えていった。相乗効果がありましたね。今もツイートは見ていますよ。
吉川 役者さんなどを僕もフォローしてチェックしているのですが、上田慎一郎監督も観客の反応を積極的にリツイートしていますね。自主的に検索しているのでしょう。
「カメラを止めるな!」アツアツファンブック本日発売です。なぜこの本がアツアツなのかって、それはカメ止めを「大好き」な人たちがつくっているからです。僕もキャストもスタッフもお客さんもカメ止めのファンなんです。どのページにも「大好き」が溢れてます。時々はみ出してます。大好き!! https://t.co/lJC9Ker8bo
— 上田慎一郎 (@shin0407) 2018年12月5日
上田監督の公式アカウントより
村山 ああいった動きは、いわゆる映画監督やキャスト陣ではないですね。事務所に所属している俳優ならば、事務所側がさせないはず。舞台挨拶の回数でいっても、過去最高かもしれません。とにかく、あらゆることが特異なんです。
「応援感」が火をつける
吉川 日本では珍しい盛り上がりを見せた『カメ止め』ですが、アメリカではSNSがプラットフォームになって火がついた事例が数多くあるといいます。たしかに、日本ではここまでの規模で広がったものは、そうそうないように感じます。なぜ『カメ止め』が最初のそれになれたのだとお考えですか?
村山 見どころが「想定外」で、ツイートも上映初期には「しゃべりたいけれどしゃべれない」といったものが多かったと思うんです。まずはそれだけ「ネタ」が秀逸だったことと、「しゃべりたくてもしゃべれない」というツイートを目にすると、見たくなりますよね。
吉川 なります。ただ、おそらく上田監督はそこまで設計していたわけではない、とは感じるのですが。
村山 そうかもしれません。ただ、彼らは純粋に映画を楽しみ、良い映画をつくりたいという熱量はあり、それが伝わっていたのは疑いようがないことです。そして、最近の日本においては「知らないものを応援したがる」みたいな傾向も感じさせます。それを後押しするのがソーシャルメディアですね。
たとえば、動画配信サイト発で、自主企画のフェスにも何万人とファンが集まり、オリコンのアルバムチャートでも1位になったりするアーティストもいます。それらもおそらく「熱量の塊」なんですね。そのライブに集まっているのがほとんど10代女子です。「知られていない世界のものを応援しよう」といった部分もファンにはあり、それがソーシャルメディア上で花開いている。「誰でも知っているものではない」ことへの応援感もある。数年前に公開されたクラウドファンディングを活用した映画も応援感がありました。
そういった部分も「火をつける要素」なのかなと。たとえば、『カメ止め』にしても10億円を掛けて作っていたら、おそらく誰も応援したがらなかったかもしれない。
吉川 応援でいうと、観る側でもリピート回数が異常な人がいますね。ほぼ毎日だとか、30回は観たというツイートもあり。そのツイートにもリスペクトが贈られたり。
村山 それも応援感のような気がするんです。観に行くことそのものが自分も『カメラを止めるな!』のキャストになったかのような一体感を生んでいるんです。
吉川 演者の曽我真臣さんなんて、舞台挨拶の途中でだいたい泣きそうになってきて、結果的に泣いちゃうみたいな……あれがまたいいですよね(笑)。みんなが同じような気持ちになるというか。
村山 ああいうの見ると、また応援したくなっちゃうんでね。その繰り返しです。
ベタな宣伝は禁じ手にした
吉川 スピード感は現在も継続している印象がありますが、拡大期に注意したことや禁止したことなど、大切にしたポイントはありますか?
村山 「ベタな宣伝」はやめようと言っていました。要は「売らんかな」という感じが伝わってはいけない。共感や共鳴している人たちが多い作品だから、それに乗ったほうがむしろいい。
たとえば、よくあるフレーズの「大ヒット上映中」は極力使うな!と宣伝部のメンバーには言っていました。8月3日の舞台挨拶に関しても「大ヒット上映中」のような垂れ幕は封印して、キャストの皆さんには自然体で壇上へ上がってもらった。「舞台挨拶をやりたい」と社内から上がってきたときにも「絶対に“大ヒット上映中”とキャストに持たせないように」と釘を刺したくらいで。
 8月3日に東京・TOHOシネマズ 日比谷で行われた「“感染”拡大公開御礼舞台挨拶」(公式Facebookページより)
8月3日に東京・TOHOシネマズ 日比谷で行われた「“感染”拡大公開御礼舞台挨拶」(公式Facebookページより)
吉川 そこまで禁じた理由は?
村山 感覚的に、「リアルなもの」を伝えていかないと本当に広がらないと思ったんです。特にTwitterはウソがバレやすい場所です。素直に全てをさらけ出すような方向で動いたほうがいいだろうと。結局、商業主義的な「メジャー路線に乗っちゃったね」といったように彼らの作品が映ると、全国配給の意味合いがずれてしまいますから。純粋に映画が好きでつくった、純粋に映画が好きで出演した、という文脈を広げたほうがいい。とにかく私たちとしても「乗っちゃった感」にはしたくなかったんですよね。
吉川 大きく解釈すると「アスミック・エースという会社は、映画が好きなんだろうな」という感じにも僕には見えました。
村山 まさにおっしゃるとおりです。アスミック・エースのブランドでこの映画をやる狙いでもありますが、「映画が本当に好きな人々が関わっているのだ」と伝われば嬉しいです。かつてはわれわれも『ニュー・シネマ・パラダイス』をはじめとした洋画の名作などを配給してきましたが、ベースにあるのは「映画が好き」という思いなんです。噂を聞きつけて公開2週目7月1日に観に行ってきっかけをつくったのも、長年いるスタッフで今は役員を務めている者ですしね。
吉川 極端に言えば、映画好きな人がどんどん増えたりとか、映画の良さを知る気持ちをみんなに思い出させたりとか、そういった願いにもつながります。
村山 そうですね。『カメ止め』は本当に映画の興行界全体にとって非常に大きな、象徴的な作品になりました。「映画が好き」という原点に戻った意味でも。
カメ止めから見る「無焦点」と「ユニゾン」の法則
吉川 良い映画であるだけでなく、誰もがスマホを手にする時代にあって、『カメ止め』には「今の時代を表す映画」というある種のイノベーティブな可能性を感じました。
われわれは「メディア環境研究所」を名乗っていますので、私たちなりに今回の現象を分析してみました。キーワードは「焦点」です。今は「単焦点」で同じメッセージを出しても刺さらないとスルーされてしまうので、コアを決めた上で「多焦点」にするとヒットにつながりやすいと考えてきました。
(参考)メディア生活フォーラム2018「情報引き寄せ」プレゼンテーションスライド

ただ、今回の『カメ止め』は「無焦点」なのだと思います。2館からスタート、無名の俳優、低予算、予備知識なしで観るべきというように、ヒットするほどに周辺情報しか出てこない。そして、SNSは周辺情報をどんどん増やすプラットフォームとして機能したんですね。「観なければコアが分からない」からこそ観客は足を運んだ。単なる「映画館で体験したほうがいいよ」という、かつてのヒット作品とつながる文脈ではないところに、僕は新しさを覚えました。

さらに、「では、なぜ観客がリピートするのか」を思うと、観ることによって周辺情報を増やす役割を自らも担いながら、「無焦点」で見えなかったコアが見えるようになり、そのコアに何度も触れたくなってくる。そして、『カメ止め』において最大のコアは「映画っていいよね」という本質的で熱い思いです。そこがマグマみたいになって熱量を発し続けることで、キャストや観客も一体となってテンションが保ち続けていたのでしょう。
村山 なるほど、たしかにコアをまっすぐに最初から伝えてしまうと、商業主義的にもなってきますね。
吉川 そうなんです。「今こそ、いい映画に出合った」みたいなメッセージを使ったりすると、先ほどの「大ヒット上映中」みたいになってしまうわけですね。
村山 今回のヒットについて私もいろいろ考えてみたときに、自分が音楽好きだからというのもありますが、「ハーモニー」と「ユニゾン」というキーワードが浮かんできました。今の映画の多くは、キャストや監督が織りなすハーモニーがきれいなメロディになって広がっている。ただ、『カメ止め』はハーモニーではなくユニゾンなんです。

吉川 おもしろい!ひたすら同じ音階をなぞるユニゾンだと。
村山 実は、ユニゾンには日本らしい部分が多分にあります。ユニゾンは強さがありながら、どこか情緒的な感じが出るんです。一般的にハーモニーのほうが音楽性は高く、ユニゾンは歌の上手さをカバーするもの……なんて言われますが、実はそうでもない。人気アイドルの歌にはユニゾンの強さがあるだけでなく、日本人が非常にユニゾンを好むことを教えてくれます。ユニゾンは斉唱ともいいますが、まさにツイートも斉唱だと思うんですよ。
吉川 ユニゾンは微妙にリズムがずれたり、音程が違っていたりするから、倍音になって豊かな感じがしてきますね。同じことを歌っているけれど、ふしぎと気持ちいい。SNSはたしかに、みんなの気持ちをユニゾンさせるプラットフォームといえますね。『カメ止め』でも、みんなが「カメ止めいいよね」「映画はいいね」と、同じことをツイートしている。
村山 日本はTwitterが特に強いと言われますが、日本におけるユニゾン文化も関係しているのではないかなと。ツイートも変にひねったものでなく、ストレートなほうが広がる感じもあります。
吉川 基本、みんなは同意していって、それが広がっていきますからね。そして、今だからこそユニゾンが面白いのだと思います。
かつての「マスの時代」は、みんながユニゾンでした。『8時だョ!全員集合』を全員が観て、「あのときの志村けんが面白かった」とユニゾンしていた。でも、現代はユニゾンができにくくなっているのでしょう。
いわゆる、スマートフォンによる体験の個人化で、みんなが同じ時間に、同じものを、同じ気持ちで、同じシチュエーションで観られなくなっている。誰も「せーの」と言い出してくれないなかで、ユニゾン性の強いプラットフォームであるTwitterだからこそ、同意を増幅させやすい。『カメ止め』は、現代においてユニゾンさせたこともイノベーティブなのだと、お話を聞いて感じました。
★後編はこちら
■プロフィール

村山直樹
ジュピターテレコム 上席執行役員 メディア事業部門長
アスミック・エース 代表取締役会長

吉川昌孝
博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所 所長































